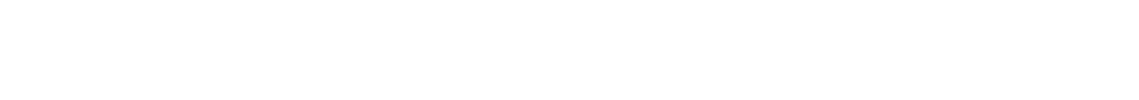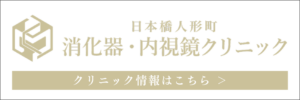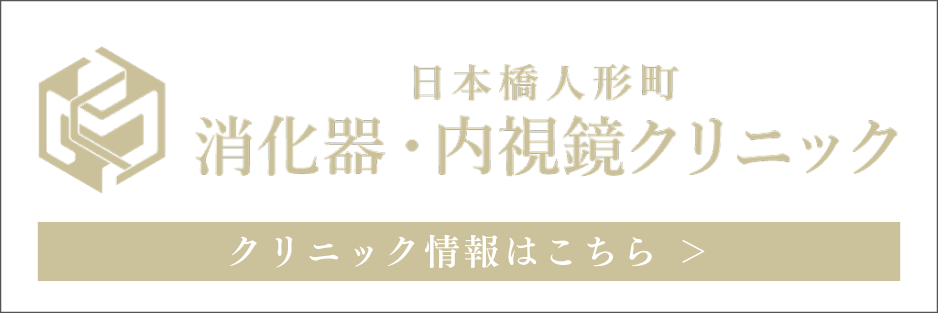2025年7月10日
胃カメラと大腸カメラを同日に受けられる「同時検査」は、忙しい方にとって時間的な負担を減らせる便利な方法です。ただし、初めての方は「本当に同時にできるの?」「どちらを先に行うの?」といった疑問もあるはず。
本記事では、同時検査の流れやメリット・デメリット、注意点を医師がわかりやすく解説します。

胃カメラと大腸カメラを同時検査とは?
胃カメラ(上部消化管内視鏡)と大腸カメラ(下部消化管内視鏡)は、別日に分けて行われることが多い検査ですが、医療機関によっては同じ日に連続して実施する「同時検査」が可能です。
この方法では、一度の受診で上下の消化管をすべて観察でき、効率的に体の状態を把握できます。
一般的には、鎮静剤を使用して患者さんの苦痛を和らげながら、まず胃カメラを行い、その後大腸カメラを実施します。検査の順番は医療機関や患者さんの状態により異なる場合もありますが、基本的には胃から大腸へと進める流れとなります。
同時に検査を受けるメリット
胃カメラと大腸カメラを同じ日に行う「同時検査」には、以下のようなメリットがあります。
-
来院回数が1回で済む
通常、別日に検査を行うと2回の通院が必要ですが、同時検査であれば1日で完結するため、時間の節約になります。 -
検査前の準備が1回で済む
大腸カメラ前には下剤を服用し、検査前にはそれぞれ絶食などの準備が必要ですが、これらを1度でまとめて行えるのも大きな利点です。 -
鎮静剤を使う場合、1回の投与で済む
鎮静剤を使用する場合、2回の検査でそれぞれ投与するよりも、1回の投与で済むため体への負担が軽減されます。 -
上下消化管の包括的な評価が可能
同日に両方を検査することで、消化管全体の状態を一度に確認でき、より的確な診断につながります。 -
精神的・身体的な負担が少ない
不安や緊張、検査後の疲労も一度で済むため、患者さんにとって負担が軽く感じられます。
このように、同時検査は忙しい方や消化器症状の全体的な精査を希望する方にとって、非常に効率的な検査方法です。
同時検査のデメリット
同時検査には多くのメリットがありますが、デメリットもあります。
以下の点を理解したうえで、実施を検討しましょう。
-
実施できる医療機関が限られる
すべての医療機関で同時検査が可能なわけではなく、設備や人員体制によって対応できない場合もあります。 -
体への負担が大きくなる場合がある
鎮静剤を使用する場合、2回の検査でそれぞれ投与するよりも、鎮静剤の総量は減るものの、1回あたりの投与量は増える場合があり、高齢者や基礎疾患のある方、麻酔に対する耐性が弱い方にとっては、長時間の検査や鎮静剤の影響が負担となることがあります。
対応している医療機関について
胃カメラと大腸カメラの同時検査は、すべての医療機関で行っているわけではありません。
対応できるかどうかは、設備や検査体制、スタッフの配置状況により異なります。
【対応している医療機関の特徴】
-
内視鏡専門医が在籍している
-
鎮静剤を使った検査体制が整っている
-
リカバリールームなどの環境が整っている
-
看護師・スタッフが十分に配置されている
このような体制の整った医療機関では、同時検査が可能であり、安全かつ効率的に実施されます。(※同時検査ができない施設が体制が不十分という意味ではありません。)
当院では同時検査に対応しています
日本橋人形町消化器・内視鏡クリニックでは、胃カメラ・大腸カメラの同時検査に対応しています。検査前の準備や流れについても、事前に丁寧にご説明しますので、安心してご相談ください。
また、同時検査の場合、内視鏡的下剤注入法による「下剤を飲まずに受けられる大腸カメラ検査」も対応可能です。大腸カメラ検査前の下剤の服用が苦手、下剤を飲みたくない方はこちらもご検討ください。
同日検査の流れと順番|どっちが先に行われる?
胃カメラと大腸カメラを同日に受ける場合、基本的な流れと検査の順番は一般的には以下の通りです(医療機関や個々の患者さんの状況によって異なる場合もあります)。
一般的な検査の流れ(自宅で下剤を服用する場合)
-
前日1日の食事制限(主に繊維質の食材などを避ける)
-
当日の朝より絶食のうえ、下剤を服用
大腸をきれいにするための準備です。
-
来院後、血圧測定・血管確保(鎮静剤の準備)
鎮静剤を使用する際には、静脈ルートの確保が必要です。 -
胃カメラを先に実施
大腸カメラの準備ができていれば、基本的に胃の中は空っぽで検査可能です。 -
続けて大腸カメラを実施
鎮静剤の効果を持続している間に、スムーズに移行します(適宜追加の投与を行い調整します)。 -
検査後はリカバリールームで休憩
鎮静剤を使用した場合は、しっかり覚醒するまで安静にします。 -
検査後の結果説明
検査後、内視鏡画像を共有しながら結果の説明を行います。
当院では、検査前に流れをご説明し、患者さんの不安を軽減するよう努めています。
検査当日の所要時間とスケジュールの目安
胃カメラと大腸カメラを同日に受ける場合、検査自体の時間に加えて前処置や休憩時間も必要となるため、全体として半日〜1日がかりとなることが一般的です。
当日のスケジュール例(自宅で下剤を服用する場合)
| 時間帯 | 内 容 |
| 6:00〜 | 下剤服用 |
| 9:45〜 | 来院・受付・問診・準備 |
| 9:55〜 | 血管確保・鎮静剤投与準備 |
| 10:00〜 | 胃カメラ検査(5〜10分程度) |
| 10:15〜 | 大腸カメラ検査(15〜20分程度) |
| 10:30〜 | 検査後の安静(30分〜1時間程度) |
| 11:30〜 | 医師からの説明・帰宅準備 |
※所要時間は個人差があります。
検査当日の注意点
-
鎮静剤使用時は自転車・車・バイクの運転不可
-
前日は夜21時以降の食事禁止、当日は朝から検査終了後まで絶食
-
大腸カメラのための下剤を当日服用
-
ポリープ切除があった場合は、検査終了後の食事や運動制限がかかる場合あり
鎮静剤(静脈麻酔)使った場合の注意点
胃カメラ・大腸カメラを同日に受ける際、多くの方が鎮静剤(静脈麻酔)を使用します。
検査時の不快感や恐怖を和らげ、スムーズに実施できる利点がありますが、安全に受けるための注意点もあります。
-
検査当日は運転禁止
鎮静剤の影響が数時間残るため、車・バイク・自転車の運転は禁止です。 -
判断力や記憶力が一時的に低下することがある
重要な予定や会議などは避け、検査後はゆっくり休むようにしましょう。 -
モニター管理が必要
血圧や脈拍、酸素飽和度をチェックしながら安全に進めるため、医療スタッフによる管理が行われます。 -
検査後にふらつき・眠気が残ることがある
リカバリールームで十分な休息をとった後に帰宅することが推奨されます。当院では検査後の麻酔の後残りが少なくなるように調整していますが、麻酔の効き具合には個人差があるため、過去に鎮静剤を聞いた際に効きが悪かった、副作用が出たなどの情報を共有いただくことが重要です。 -
ご高齢の方や持病のある方は医師と要相談
呼吸抑制や血圧低下のリスクがあるため、個別の対応が必要です。
当院では、鎮静剤を使用する場合にも万全の体制を整え、安心して検査を受けられるよう配慮していますが不安な点や希望があれば、事前にお気軽にご相談ください。

同時検査にかかる費用と保険適用について
胃カメラ・大腸カメラを同時に受ける際の費用は、保険診療か自費診療か、また検査中にポリープ切除などの処置を行うかによって変動します。
保険適用となる条件
-
医師の判断により検査が「必要」とされた場合
-
症状(腹痛、便通異常、出血など)があり、診断目的で行う場合
このようなケースでは健康保険が適用され、自己負担は通常3割(高齢者は1〜2割)となります。
検査費用の目安(3割負担の場合)
| 内 容 | 自己負担額の目安(3割負担の場合) |
| 胃カメラ・大腸カメラ同時検査 (観察のみ) | 12,500円前後 |
※金額はあくまで目安で、使用する薬剤や検査内容により変動します。
自費診療の場合
健診目的など、症状がなく本人希望で実施する場合は保険適用外となり、全額自己負担となります。
自費診療の価格設定は医療機関により大きく異なりますので、事前に確認の上で検査を受けるようにしてください。
胃カメラ・大腸カメラ同時検査をおすすめする方
胃カメラと大腸カメラを同時に受けるべきかどうかは、患者さんの症状やリスクに応じて判断されます。
以下のような方は、同日での検査が特におすすめです。
-
消化器症状が上下にわたって出ている方
例:胃の痛みと便通異常、吐き気と下血など、複数の消化器症状が同時にある場合。 -
胃がん・大腸がんの家族歴がある方
早期発見・早期治療のため、上下消化管の検査を一度に行うのが有効です。 -
40歳以上で一度も内視鏡検査を受けたことがない方
年齢的に消化管の病気のリスクが上がるため、予防的な意味でも同時検査が勧められます。 -
仕事や育児で複数回の通院が難しい方
来院回数や検査準備を1回で済ませたい方にとって、同時検査は大きなメリットとなります。 -
人間ドックなどで異常を指摘された方
精密検査として一度に受けることで、速やかな診断と対応が可能になります。
まとめ
胃カメラと大腸カメラの同時検査は、上下の消化管を一度に確認できる効率的な検査方法です。特に多忙な方や、胃腸に複数の症状がある方にとって、通院回数や身体的・精神的負担を軽減できる大きなメリットがあります。
一方で、医療機関の選び方なども理解しておく必要があります。安全かつスムーズに検査を受けるためには、事前の説明と準備が非常に重要です。
当院では、同時検査を希望される方にも丁寧に対応し、患者さんの不安や疑問に寄り添った診療を心がけています。胃腸の不調が気になる方は、ぜひお気軽にご相談ください。
よくある質問
いいえ、症状やご希望によって別日に分けることも可能です。体調や生活スタイルに合わせて医師と相談の上で決定しましょう。
可能ではありますが、検査の負担が大きくなるため、当院では鎮静剤の使用をおすすめしています。特に咽頭観察では鎮静剤の使用により、がんの発見率が向上することが論文報告されています。これは反射が起きると喉の筋肉が収縮し、観察が難しくなる部分があるためです。
一般的に鎮静剤を使用した場合は、当日の運転や重要な作業は避け、できるだけ安静に過ごすことが推奨されます。翌日以降は通常通りの生活が可能です。当院は土地柄、検査後に仕事に出勤される方も多くいらっしゃいます。その場合は鎮静剤の量や種類を調整しますので事前にお申し付けください。
明確な年齢制限はなく、20代〜80代の幅広い年代の方が同時検査を受けられています。ただし、検査の必要性や、持病の有無などによっても異なりますので、診察時に個別に判断させていただいております。
基本的には生理期間中でも検査を受けることは問題ありません。ただし月経痛が重い場合や体調不良がある場合には無理せず、日程調整をおすすめします。