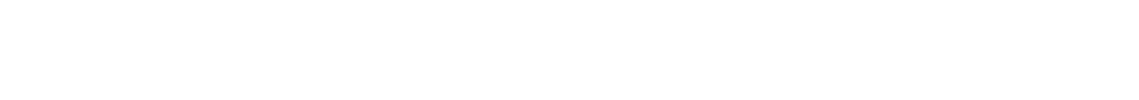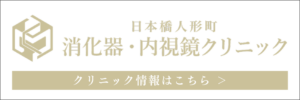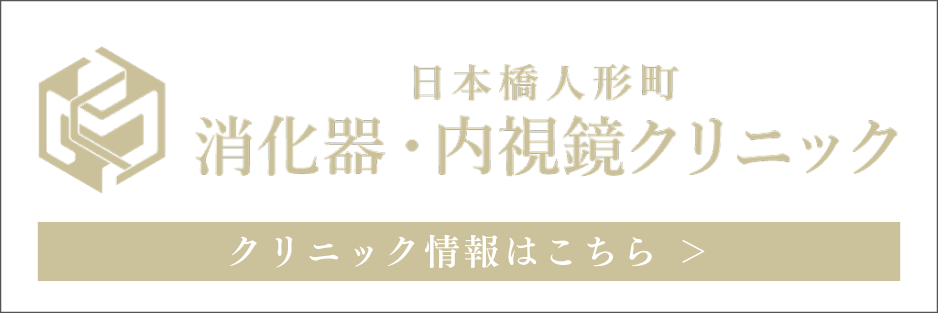2025年7月11日
クローン病は、食事との関係が深い病気です。「何を食べればよいのか」「どんな食品を避けるべきか」と悩まれる方も多いのではないでしょうか。食事内容によって症状が悪化したり、逆に安定したりするため、日々の食生活が非常に重要になります。
本記事では、クローン病と食事の関係、避けたい食品やおすすめの食材、外食時の注意点まで、医師の視点でわかりやすく解説します。

クローン病とは?
クローン病は、口から肛門まで全ての消化管に慢性的な炎症を起こしうる炎症性腸疾患(IBD)の一つです。
主に小腸や大腸に症状が出ることが多く、10代後半から30代での若年者の発症が多く、男女問わずみられます。原因は完全には解明されていませんが、免疫異常や遺伝的要因、腸内細菌の影響などが関与していると考えられています。
症状としては、腹痛や下痢、体重減少、発熱、肛門の病変などが見られ、慢性的に繰り返すのが特徴です。また、病変は口から肛門まであらゆる部位に現れる可能性があるため、症状の現れ方にも個人差があります。
クローン病は現段階で完治させる治療法はない難しい病気ですが、適切な治療と食事管理により、症状をコントロールしながら日常生活を送ることを目指します。その中でも「食事」は治療の一環として非常に重要な役割を担います。
クローン病と食事の関係
クローン病の症状は、食事の内容によって悪化することがあります。
特に発症や再燃のきっかけとして、高脂肪食や乳製品、香辛料などが指摘されており、これらの摂取により腸粘膜への刺激が強くなると、炎症が悪化しやすくなります。
ただし、すべての患者が同じ食品に反応するわけではなく、個人差が大きいため、自分に合った食事パターンを見つけることが重要です。症状が落ち着いている「寛解期」と、症状が強く出る「活動期」とでも食事の注意点は異なります。
また、腸管が炎症を起こしている状態では、栄養の吸収効率が落ちるため、必要なエネルギーや栄養素をバランスよく補う必要があります。消化にやさしい食事を基本としつつ、体への負担を抑えながら、必要な栄養を摂取することが、クローン病とうまく付き合う上でのカギとなります。
クローン病におすすめの食事
クローン病の方には、腸への負担が少なく、消化吸収のしやすい食事が推奨されます。特に以下のような食材や調理法が適しています。
【おすすめの食事例】
-
低脂肪のたんぱく質源
鶏ささみ、白身魚、豆腐など
-
やわらかく煮た野菜
にんじん、大根、かぼちゃなど(皮・繊維は除く)
-
エネルギー補給源
うどん、おかゆ、白米などの消化の良い炭水化物
-
発酵食品(少量)
味噌やヨーグルト(乳糖不耐がない場合)
また、食物繊維の摂取については注意が必要です。活動期には繊維を控えるべきですが、寛解期には便通の改善や腸内環境の調整のために、少量ずつ取り入れても構いません。
一度に多くを食べるのではなく、少量を回数多く摂る「分食」が体への負担を軽くします。さらに、よく噛んでゆっくり食べることも、消化を助ける大切なポイントです。
クローン病で避けた方がよい食品・成分一覧
クローン病では、腸への刺激や炎症を引き起こす可能性のある食品を避けることが大切です。
とくに以下の食品・成分は、活動期や体調が不安定なときには控えるようにしましょう。
| 食品・成分 | 理 由 |
| 脂肪分の多い肉(豚バラ・牛カルビなど) | 消化に時間がかかり腸を刺激しやすい |
| 揚げ物・スナック菓子 | 高脂肪・高添加物で炎症を悪化させる |
| 香辛料・刺激物(唐辛子・カレーなど) | 腸粘膜への刺激が強い |
| 乳製品(牛乳・チーズなど) | 乳糖不耐の人では下痢の原因に |
| アルコール・カフェイン飲料 | 脱水・刺激作用がある |
| 繊維質の多い野菜(ごぼう・セロリなど) | 活動期には腸管を傷つける可能性あり |
体調が落ち着いている寛解期であっても、摂取する場合は少量から始めて様子をみるようにしましょう。症状が悪化する場合は、速やかに中止し医師に相談してください。
外食・コンビニ・市販食品の選び方と注意点
クローン病の方にとって、外食やコンビニ・市販食品の利用は難しく感じるかもしれませんが、選び方次第で比較的安全に取り入れることが可能な場合もあります。以下のポイントを参考にしてください。
-
脂質の少ないメニューを選ぶ
蒸し鶏、煮魚、うどん、おにぎり(具材に注意)など
-
揚げ物やこってり系は避ける
とんかつ、ラーメン、カレーなどは要注意
-
原材料表示を確認
食品添加物や香辛料が多いものは避ける
-
加工食品は少量から
コンビニ弁当やレトルト食品は、体調が安定しているときに様子を見ながら
また、コンビニでは、おにぎり(具が梅・鮭など)、バナナ、プレーンヨーグルト(乳糖に注意)、豆腐などが比較的安心です。汁物も、脂肪分の少ない味噌汁やスープなら取り入れやすいでしょう。
外出先での食事は無理をせず、体調に合わせて安全な選択を心がけましょう。
調理法や食事の工夫で体への負担を減らすコツ
クローン病の方は、同じ食材でも調理法によって腸への負担が大きく変わるため、日々の調理に工夫を取り入れることが重要です。以下のようなポイントを意識してみましょう。
-
油を使わない調理法を選ぶ
蒸す、茹でる、煮るなどの調理法がおすすめ
-
繊維質はカット&加熱
野菜は皮をむき、やわらかく煮てから使用
-
食材を細かくする
ミンチ肉やペースト状にすることで消化がしやすくなる
-
調味料は控えめに
塩分や香辛料の強い味つけは避ける
-
一度に食べすぎない
腹八分目を意識し、1日5~6回に分けて食べる「分食」が効果的
また、できるだけ食材は新鮮なものを選び、消化に時間のかかる加工食品は避けるようにしましょう。日々のちょっとした工夫が、腸への負担を減らし、症状の安定につながります。
クローン病と付き合うための生活習慣
クローン病は長期的に付き合っていく必要がある病気だからこそ、食事だけでなく生活習慣全体を見直すことが大切です。以下のような習慣が、病状の安定に役立ちます。
-
自分に合った食事を知る
症状が出たときの食事内容を記録する「食事日記」が有効
-
体調に合わせて柔軟に対応
無理せず休息をとり、無理な外食は避ける
-
適度な運動を取り入れる
散歩などの軽い運動はストレス軽減にもつながる
-
十分な睡眠と休養を確保
体の回復力を高め、免疫バランスを整える
-
ストレスをためない
過度なストレスは再燃のリスクになるため、リラックスできる時間を意識的に作る
まとめ
クローン病は、日々の食事や生活習慣によって症状の安定や悪化に大きく影響を受ける疾患です。自分の体調に合った食材や調理法を見つけ、腸にやさしい食生活を心がけることが、再燃の予防や症状のコントロールにつながります。
食事では、低脂肪・低刺激・消化の良いものを中心に選び、体調に応じて摂取を調整することが大切です。外食や市販食品を利用する際も、成分表示を確認しながら慎重に選びましょう。
また、無理のない生活リズムやストレス対策、定期的な受診も忘れず、医師と連携しながら病気と向き合っていくことが重要です。
クローン病と長く付き合っていくためには、「食事」と「生活」の両面からバランスよく見直し、安心して暮らせる環境を整えていくことが何よりの対策です。
よくある質問
ある程度の食材は取り入れられますが、急な再燃を防ぐためにも高脂肪・高刺激の食品は控えめにするのが望ましいです。体調に応じて少しずつ試し、合わないものは避けましょう。
食事は重要な要素ですが、あくまでも補助的な役割です。薬物療法と合わせて、医師の指導のもとで食事を調整することが必要です。自己判断での極端な制限や無理な療法は避けましょう。
外食が続く場合は、油ものや香辛料を避け、できるだけシンプルな調理法のメニューを選びましょう。また、調子が悪くなったときに備えて、低脂肪のおにぎりやレトルトのおかゆを常備しておくのも一つの方法です。
活動期は避けた方がよいですが、寛解期にはやわらかく調理された野菜や少量の水溶性食物繊維なら取り入れ可能です。ただし、狭窄の有無など腸管の状態に大きな個人差があるため、かかりつけ医の指示に従ってください。
医師の指導のもとであれば、消化吸収の良い製品は補助として有効に活用できます。高脂肪・高糖質の製品は避け、低刺激のものを選びましょう。