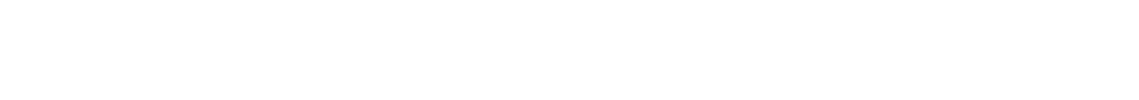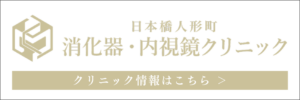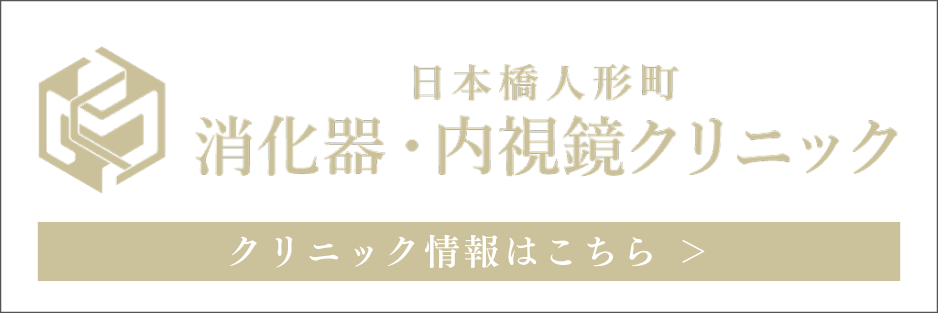2025年8月18日
胸やけやのどの違和感、食後の不快感など、逆流性食道炎の症状に悩まされていませんか?忙しい日々の中で病院を受診する時間が取れず、「市販薬で少しでも楽になれば」と考える方は多いでしょう。
本記事では、逆流性食道炎に効く市販薬の種類や選び方、使う際の注意点まで、医師の視点からわかりやすく解説します。症状を和らげたい方、自己判断で市販薬を使って良いか悩んでいる方は、ぜひご一読ください。

逆流性食道炎とは?
逆流性食道炎とは、胃酸や胃の内容物が食道へ逆流し、食道の粘膜に炎症を引き起こす病気です。本来、胃は強い酸で食べ物を消化する働きがありますが、胃酸は本来食道に存在しないため、この胃酸が食道に逆流すると、粘膜を刺激して炎症を生じ、さまざまな不快な症状が現れます。
主な症状には以下のようなものがあります。
-
胸やけ(みぞおち付近の焼けるような痛み)
-
のどの違和感やイガイガ感
-
食べ物や水分を飲み込んだ際のつかえ感(嚥下困難感、咽頭異物感)
-
乾いた咳
-
酸っぱい液体(や苦い液体)が口まで上がってくる感じ(呑酸)
食生活の乱れやストレス、肥満、姿勢(前かがみなど)などが原因となりやすく、日本でも年々患者数が増加傾向にあります。軽症であれば市販薬によるセルフケアが可能な場合もありますが、重症化すると治療が長引くこともあるため、早めの対策が重要です。
市販薬で逆流性食道炎の症状は治せる?
逆流性食道炎の症状が軽度であれば、市販薬で症状を緩和できるケースがあります。
ただし、「治す」というよりは「一時的に症状を抑える」ことが目的であり、病気の原因そのものを取り除くわけではありません。逆流性食道炎の根本的な原因は、胃酸の逆流や下部食道括約筋(LES)の機能低下、食道の運動機能障害などであり、生活習慣の改善や医師による適切な治療が必要なことも多いです。
市販薬で期待できる効果は以下のようなものです。
-
胃酸の分泌を抑える
-
胃酸を中和する
-
食道や胃粘膜の炎症を抑える
市販薬で症状が改善しない場合や、繰り返すような症状がある場合は、自己判断での継続使用は避け、早めに医療機関を受診することが大切です。市販薬はあくまで応急的な手段と理解し、適切なタイミングで専門医に相談しましょう。
逆流性食道炎の市販薬の種類と特徴
逆流性食道炎の市販薬は、主に症状を和らげることを目的としており、以下のような種類があります。
それぞれの薬に異なる作用機序があるため、自身の症状に合った種類を選ぶことが大切です。また、市販薬にも服用上の注意点があるため、添付文書をよく読み、適切な使い方を心がけましょう。
胃酸分泌抑制薬(H2ブロッカー)
胃酸の分泌を抑えることで、食道への刺激を減らします。
効果は数時間持続し、就寝前の胸やけに適しています。
制酸薬(炭酸水素ナトリウム、水酸化マグネシウム、炭酸カルシウムなど)
胃酸を中和し、胃内の酸度を下げる作用があります。
即効性があり、食後の不快感に向いています。
胃粘膜保護薬(スクラルファートなど)
胃や食道の粘膜をコーティングして保護する役割があります。
炎症や荒れた粘膜を保護し、修復を促します。
漢方薬(半夏瀉心湯、六君子湯など)
胃腸の機能を整え、胃もたれ・吐き気・胸やけなどを改善する作用があります。
半夏瀉心湯は、消化不良や食べたものが胃に長く残る感じ(胃の動きが弱い状態)に伴う胸やけや吐き気に適しています。六君子湯は、胃の働きを活発にし、食欲不振や胃もたれ症状の改善に用いられます。
市販されている逆流性食道炎向けの総合胃腸薬の中には、複数の成分を組み合わせた製剤があります。例えば、H₂ブロッカー+制酸薬や制酸薬+胃粘膜保護薬+消化酵素などです。一つ一つの効能は、処方薬には劣りますが、一度に複数の作用(酸分泌抑制・酸中和・粘膜保護)を得られるため、幅広い症状に対応しやすいのが特徴です。
症状タイプ別|おすすめの市販薬の選び方
逆流性食道炎の症状は人によって異なるため、症状のタイプに応じて市販薬を選ぶことが重要です。
以下に主な症状別のおすすめ薬を紹介します。
| 症状 | おすすめ薬 | 期待できる効果 |
|---|---|---|
| 胸やけがつらい | 胃酸分泌抑制薬 (H2ブロッカー) | 胃酸の分泌を抑えることで、胸やけの原因となる胃酸の逆流を防ぎます。 |
| のどの違和感・咳 | 胃粘膜保護薬 | 逆流した胃酸が食道やのどの粘膜を刺激することで症状が出るため、粘膜を保護する薬が有効 |
| 食後の胃もたれ・逆流感 | 制酸薬 | 胃酸を中和し、胃内の圧力を下げることで逆流を抑えます。 |
| 食後に胃が重たい むかつきがある ストレスが多い | 漢方薬(半夏瀉心湯) | 胃腸の動きを整え、食べ物が胃に長く残る状態を改善し、胸やけや吐き気をやわらげます |
| 体力が落ちて食欲がない 疲れやすい 少し食べただけでお腹がいっぱいになる | 漢方薬(六君子湯) | 胃の働きを活発にし、消化吸収を助けます |
市販薬を使う際の注意点
逆流性食道炎の市販薬は便利な反面、正しく使用しないと効果が得られないだけでなく、副作用や症状の悪化を招く可能性もあります。
市販薬はあくまで一時的な症状の緩和を目的としたものであり、根本的な治療ではありません。安全に使うためにも、自分の体調や症状をよく観察しながら、必要に応じて医師の診察を受けることが大切です。
以下の点に注意して使用しましょう。
-
使用前に必ず添付文書を確認
成分や使用上の注意、副作用情報などを把握し、用法用量を守って服用しましょう。
-
症状が続く場合は自己判断での服用を続けない
2週間以上服用しても改善しない場合や症状が悪化する場合は、早めに医療機関を受診してください。
-
他の薬との併用に注意
処方薬や他の市販薬と併用すると、効果が弱まったり副作用が出る可能性があります。服用中の薬がある場合は必ず薬剤師や医師に相談してください。
-
妊娠中・授乳中の方や高齢者は医師に相談を
薬の影響を受けやすいため、自己判断での服用を避けましょう。
まとめ
逆流性食道炎は、胃酸の逆流によって食道に炎症が起こる病気であり、胸やけやのどの違和感、胃もたれなどの症状が現れます。軽度であれば市販薬で一時的な症状の緩和は可能ですが、根本的な治療には生活習慣の見直しや、必要に応じた処方薬が欠かせません。
市販薬には「胃酸分泌抑制薬」「制酸薬」「胃粘膜保護薬」「漢方薬」などがあり、症状に合わせて選ぶことが大切です。ただし、長期間の自己判断による使用は避け、改善が見られない場合は早めに医師へ相談しましょう。
市販薬はあくまで「応急的な対処法」であり、再発防止や重症化を防ぐには、医師の診断と治療が不可欠です。症状が続くようであれば、専門医の診察を受けることをおすすめします。
よくある質問
軽度であれば生活習慣の改善や市販薬の使用により、自然に症状が落ち着くこともあります。しかし、症状が繰り返す場合や重症化している場合は、医師による診察と治療が必要です。
一般的には、2週間以内の使用が目安とされています。それ以上続けても症状が改善しない場合は、必ず医療機関を受診してください。
脂っこいもの、刺激物、アルコール、カフェインの摂取は控えめにし、食後すぐに横にならないことが大切です。1回の食事量を減らし、よく噛んでゆっくり食べる習慣も効果的です。
消化器内科を受診するのが最適です。当院のような内視鏡検査に対応したクリニックであれば、必要に応じて食道の状態を詳しく確認できます。