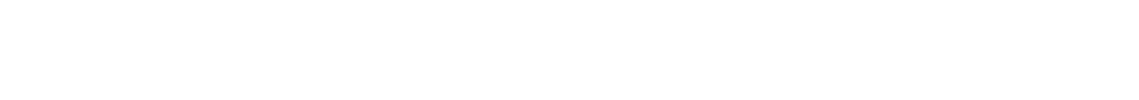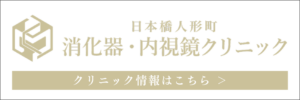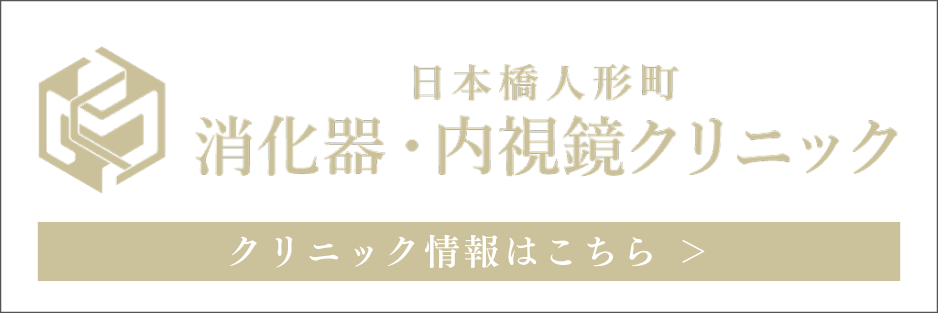2025年9月18日
「げっぷが止まらない」と感じたことはありませんか?一時的な生理現象であれば心配はいりませんが、頻繁に続く場合や他の症状を伴う場合には、胃や食道など消化器系の病気が隠れていることもあります。
本記事では、げっぷが止まらないときに考えられる原因や、医療機関を受診すべき症状、自宅でできる改善方法、予防のポイントまで、消化器専門クリニックの視点からわかりやすく解説します。

げっぷが止まらないときに考えられる原因
げっぷは、胃の中に溜まった空気が食道を通って口から排出される自然な現象です。
しかし、げっぷが頻繁に止まらない場合には、いくつかの原因が考えられます。
-
食事のスピードが早い
-
よく噛まずに一気に飲み込む
-
炭酸飲料やビールなどガスが多い飲み物を好んで飲む
-
ガムや飴をよく噛む・なめる
-
食事中や直後に会話の機会が多い
-
姿勢が悪い、猫背になりがち
-
精神的ストレスや緊張状態が続いている
こういった生活習慣では、知らず知らずのうちに空気を胃や腸内に多く取り込んでしまいます。
げっぷで受診が必要な症状は?
げっぷそのものは生理現象で問題ない場合が多いですが、次のような症状があれば医療機関の受診を検討しましょう。
-
胸やけ、胸の痛みがある
-
みぞおち周辺や胃の痛みが強い
-
お腹が張ってつらい
-
吐き気・嘔吐が続く
-
食欲がなくなった、体重が急激に減少した
-
物を飲み込むときに詰まる感じや違和感がある
-
吐いた物に血が混じる、黒いタール状の便が出る
げっぷが数週間以上続く場合や、生活改善をしても症状が良くならない場合も受診の目安です。特に高齢の方や家族に消化器疾患の既往がある方は、早めに専門医へ相談することをおすすめします。
自宅でできるげっぷの改善法
げっぷは日常生活の工夫で軽減できることがあります。以下のポイントを意識してみましょう。
食事の工夫
一口ずつゆっくりよく噛んで食べる
早食いや大きな口でかき込む食べ方を避ける
炭酸飲料・ビール・ガム・飴など、空気を多く取り込みやすいものを控える
高タンパク食や刺激物(香辛料)の食品は避ける
食後の過ごし方
-
食後すぐに横にならない
-
上半身をやや高くして座り、逆流を防ぐ
リラックスを心がける
-
深呼吸、ストレッチ、ぬるめの入浴などを取り入れる
-
ストレスを溜めない工夫をする
生活習慣の見直し
-
腹部を締め付ける服装を避ける
-
禁煙や飲酒量の節度を守る
-
日々の軽い運動や散歩で腸の動きを促す
-
便秘を予防する
これらの方法は、空気を余分に飲み込むことを防ぎ、胃への負担を減らす効果があります。症状が軽度であれば、日常生活のちょっとした工夫で改善できることも多いため、まずは試してみることをおすすめします。
日常生活での予防・習慣の見直し
げっぷを繰り返さないためにも、生活習慣の見直しはとても大切です。
-
1日3食を規則正しく摂る
-
バランスの良い食生活を心がける
-
脂っこいもの、刺激の強い食品(香辛料やカフェインなど)は控えめに
-
タンパク質の摂りすぎに注意する
-
野菜や果物、海藻など食物繊維をしっかり取り入れ、便秘を防ぐ
-
寝る前や夜遅くの食事は控える
-
良質な睡眠を取る
-
日頃からこまめに体を動かし、長時間同じ姿勢をとらない
-
こまめな水分補給を心がける
生活習慣の見直しは、げっぷだけでなく、胃もたれや胸やけなどの消化器症状全般の予防にもつながります。
小さな習慣改善が将来的な病気予防にも役立つため、日々の生活に無理なく取り入れていくことをおすすめします。
げっぷが長く続くときの検査と治療
げっぷが長く続く場合、医療機関では次のような流れで検査と治療を行います。
-
初期診察
問診と診察で、症状の経過・頻度・食生活や生活リズムを詳しく確認
-
検査
胃カメラ(上部消化管内視鏡検査)で胃・食道・十二指腸を丁寧に観察
消化性潰瘍や腫瘍(がん)が疑われる場合は、生検(組織検査)を実施
治療は原因に応じて行われます。胃酸の分泌を抑える薬、胃腸の運動を整える薬などの内服治療が中心ですが、生活習慣の改善指導も並行して行います。
一般的な治療が奏功しない場合などは必要に応じて、胃酸の分泌状態や食道の動きを調べる検査を追加します(特殊な医療機関でのみ実施可能)。
げっぷの症状は何科を受診する?
げっぷが続く場合、まず受診を検討すべきは消化器内科です。
消化器内科では、胃や食道、大腸といった消化管全体の診察・検査が可能で、逆流性食道炎や胃潰瘍など多くの原因疾患を見極めることができます。
特に「胸やけ」「体重減少」「血便」といった症状を伴う場合は、早めに消化器内科での精密検査が推奨されます。まずは専門性のある消化器内科で原因を特定し、必要に応じて他科と連携した治療を受けるのが安心です。
まとめ
げっぷは一時的なものであれば心配はいりませんが、頻繁に続く場合や胸やけ・体重減少など他の症状を伴う場合には、消化器系の病気が隠れている可能性があります。
自宅でできる工夫としては「食事の仕方を見直す」「炭酸飲料を控える」「姿勢を整える」などがあり、軽度であれば改善が期待できます。しかし症状が長引くときは、消化器内科で検査を受け、原因を特定して適切な治療を行うことが大切です。日常生活の小さな工夫と専門医での診察を組み合わせることで、安心して症状の改善につなげていきましょう。
よくある質問
ストレスの可能性もあります。ストレスは胃酸過多の要因となりやすく、お腹の張りやげっぷを引き起こします。ストレスや緊張で無意識に空気を飲み込んでしまう「呑気症」が原因となることもあります。
胃酸を抑える薬などで一時的に症状が軽減することはありますが、長引く場合は必ず医師に相談してください。
基本的には心配ありませんが、腹痛や食欲不振を伴うときは小児科の受診がおすすめです。
早食いや炭酸飲料の摂取、食後すぐ横になるなどで空気がたまりやすくなるためです。
逆流性食道炎などの病気が関係している可能性が高いため、消化器内科での検査を受けましょう。