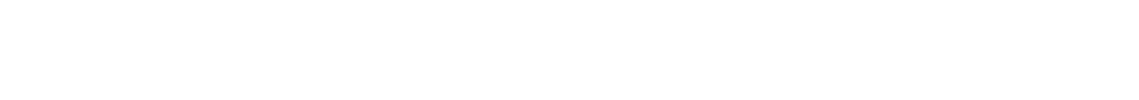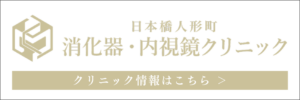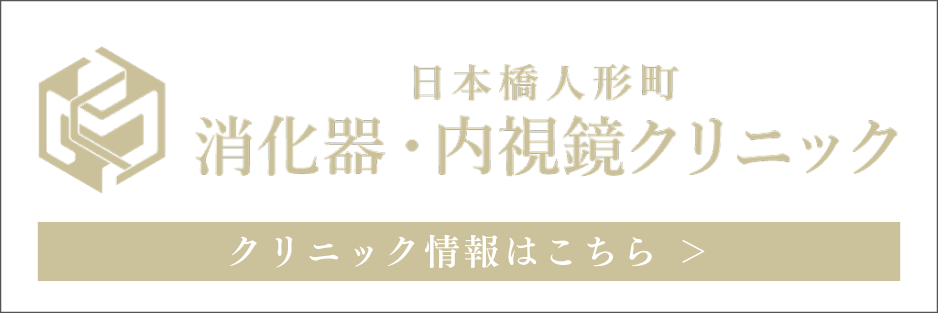2025年9月21日
胃腸炎は「お腹の風邪」とも呼ばれ、急な下痢や嘔吐、発熱などを引き起こす身近な病気です。しかし一方で、「人からうつるのか?」「どのくらいで症状が出るのか?」といった疑問を抱く方も少なくありません。特にノロウイルスやロタウイルスが原因となる場合は、強い感染力を持つため、家庭内や職場、学校で広がることもあります。
本記事では、胃腸炎の特徴や感染の有無、潜伏期間、予防法までを医師の視点からわかりやすく解説します。

胃腸炎について
胃腸炎とは、胃や腸の粘膜に炎症が生じることで、下痢・嘔吐・腹痛・発熱などを起こす病気の総称です。
原因はさまざまで、代表的なのは「感染性胃腸炎」と呼ばれるウイルスや細菌によるものです。特に冬季に流行するノロウイルスや、乳幼児に多いロタウイルスはよく知られています。また、細菌性の場合はサルモネラ菌やカンピロバクターが原因になることがあります。
非感染性の胃腸炎としては、暴飲暴食、過度なアルコール摂取、薬の副作用、食物アレルギーなどでも起こります。症状は数日で治まることが多いですが、脱水や重症化することもあるため注意が必要です。
胃腸炎はうつる?
胃腸炎には「感染するもの」と「感染しないもの」があります。特に注意が必要なのは、ウイルスや細菌によって起こる感染性胃腸炎です。
代表的なものにノロウイルスやロタウイルスがあり、これらは強い感染力を持っています。
感染経路は以下の通りです。
-
飛沫感染
嘔吐物が乾燥し、飛び散った粒子を吸い込む -
接触感染
嘔吐物や便に触れた手や物を介して口に入る -
食事からの感染
ウイルスや細菌に汚染された食品や水を摂取する
一方で、暴飲暴食や薬の副作用による胃腸炎は人から人へうつることはありません。
特に感染性のものは家庭や学校、介護施設などでは、嘔吐物や便の適切な処理が不十分だと一気に感染が拡大することがあります。
そのため、胃腸炎と診断された場合は、原因を見極めて「うつる可能性があるのか」を理解することが重要です。感染性の場合は、手洗いや食器の消毒、マスク着用などの徹底が求められます。
潜伏期間について
胃腸炎の潜伏期間は原因となる病原体によって異なります。潜伏期間とは、病原体に感染してから実際に症状が現れるまでの期間を指します。
代表的なウイルス・細菌の潜伏期間は以下の通りです。
| 原因 | 潜伏期間 | 特徴 |
| ノロウイルス | 1〜2日 | 非常に強い感染力。冬季に流行しやすい |
| ロタウイルス | 1〜3日 | 1〜3日 乳幼児に多い。白っぽい下痢便が特徴 |
| サルモネラ菌 | サルモネ菌 6〜72時間 | 鶏卵や食肉が原因になりやすい |
| カンピロバクター | 2〜5日 | 鶏肉の加熱不足で感染。腹痛が強いことが多い |
| 病原性大腸菌 | 1〜5日 | 食中毒として知られ、発熱や血便を伴うことも |
潜伏期間中は症状がないため、本人は気付かないまま周囲にうつしてしまう可能性があります。特にノロウイルスやロタウイルスは、症状が出る前からウイルスを排出している場合もあるため、集団生活の場では感染拡大を防ぐ対策が重要です。
感染力の強さ
| ウイルス | 感染力 |
| ノロウイルス | 極めて強い。症状が軽くても感染を広げる |
| ロタウイルス | 子どもに多く、家族内感染が起こりやすい |
| 細菌性(サルモネラなど) | 食品や水を介して集団感染が発生する |
腸炎の中でも、特にノロウイルスは非常に強い感染力を持つことで知られています。わずか100個程度のウイルスでも発症することがあり、飛沫や接触、食品を介して容易に広がります。嘔吐物や便の中には大量のウイルスが含まれ、処理が不十分だと周囲に拡散しやすいため注意が必要です。
ロタウイルスも強い感染力を持ち、特に乳幼児の間で流行します。家庭内で一人が発症すると、看病する家族やきょうだいに次々とうつるケースも少なくありません。
細菌性胃腸炎の場合も、汚染された食品や水を介して集団感染を引き起こすことがあります。
胃腸炎にかかったときの対応
胃腸炎にかかった際は、まず脱水予防を最優先にしましょう。下痢や嘔吐が続くと体内の水分と電解質が失われ、特に子どもや高齢者では重症化のリスクが高まります。経口補水液(ORS)やイオン飲料を少しずつこまめに摂取することが大切です。
食事は無理に摂らず、症状が落ち着いてから消化の良いもの(おかゆ、うどん、バナナなど)を少量ずつ再開すると安心です。乳幼児の場合は母乳やミルクを続けながら水分補給を工夫しましょう。
また、安静にして十分な休養を取ることも重要です。胃腸薬や整腸剤を使う場合は、自己判断せず医師の指示を受けるようにしてください。
高熱、血便、強い腹痛、嘔吐が続くといった症状がある場合は、細菌感染や他の病気の可能性もあるため、早めの受診をおすすめします。
家庭内では、嘔吐物や便を適切に処理し、手洗いや消毒を徹底することで周囲への感染拡大を防げます。
胃腸炎をうつさないための予防法
胃腸炎は家庭や学校、職場などで一気に広がる可能性があるため、予防対策がとても重要です。特にノロウイルスやロタウイルスは感染力が強く、わずかな油断で周囲に拡大してしまいます。
以下の点を徹底することで、うつさない工夫ができます。
-
こまめな手洗い
石けんと流水で20秒以上、特にトイレや調理前後は念入りに -
アルコール消毒だけでは不十分
ノロウイルスにはアルコールが効きにくいため、次亜塩素酸ナトリウム(塩素系漂白剤)の希釈液で消毒する -
嘔吐物・便の処理
使い捨て手袋・マスクを使用し、ペーパータオルで拭き取り、適切に廃棄 -
食品の加熱
中心温度85℃以上で1分以上加熱することで多くのウイルスや細菌は不活化される -
タオルや食器の共用を避ける
家族間感染を防ぐために専用に分ける
また、感染者は症状が治まってからも数日間はウイルスを排出していることがあるため、回復期でも注意が必要です。普段から手洗いと衛生管理を習慣づけることが最大の予防策になります。
まとめ
胃腸炎は、ウイルスや細菌、または生活習慣などさまざまな原因で起こる病気です。特に感染性胃腸炎は強い感染力を持ち、家庭や学校、職場などで急速に広がることがあります。多くの場合、数日で自然に回復しますが、体力が落ちている方では重症化する可能性もあります。
ポイントを整理すると以下の通りです。
-
胃腸炎には感染するものとしないものがある
-
潜伏期間は原因によって異なり、症状が出る前から感染を広げることもある
-
感染力が非常に強い病原体(ノロ・ロタウイルスなど)がある
-
罹患時は水分補給と安静が基本。重症化が疑われる場合は受診が必要
-
手洗いや食品の加熱、適切な消毒が感染拡大防止に重要
感染を防ぐ意識と、適切な対応を心がけることが大切です。
よくある質問
いいえ。ウイルスや細菌による感染性胃腸炎はうつりますが、暴飲暴食や薬の副作用によるものはうつりません。
はい。特にノロウイルスは症状が出る前からウイルスを排出することがあり、注意が必要です。
おかゆ、うどん、バナナ、りんごなど消化の良い食べ物を少量ずつ摂りましょう。無理に食べる必要はありません。
下痢や嘔吐などの症状が治まり、体調が安定してからが目安です。感染拡大防止のため、医師の指示に従うと安心です。
手洗いの徹底、タオルや食器の共用を避ける、嘔吐物や便の適切な処理と消毒が効果的です。