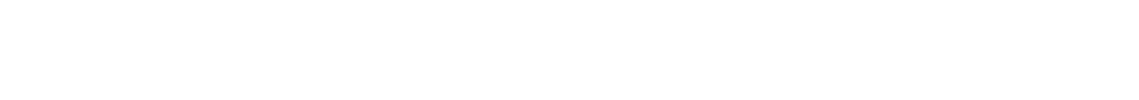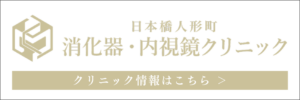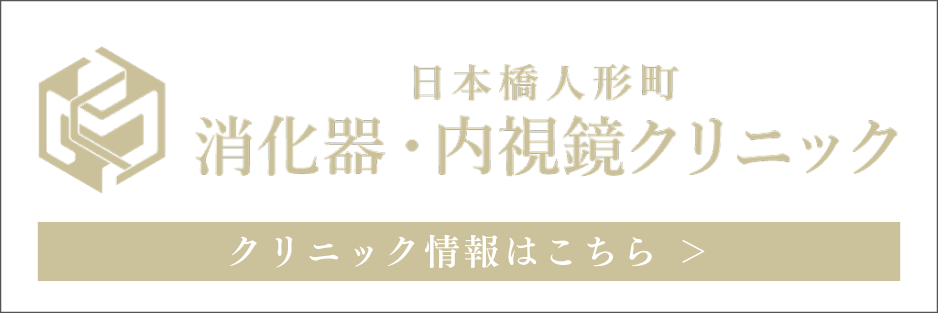2025年5月21日
主に冬場に流行する「ノロウイルス」は、強い感染力と突然の激しい嘔吐・下痢などの症状で知られています。特に子どもや高齢者にとっては重症化するリスクもあるため、早期の対応が重要です。
本記事では、ノロウイルスの基本的な情報から症状・感染経路・予防法・受診の目安までをわかりやすく解説します。

ノロウイルスとは?
ノロウイルスは、感染性胃腸炎の原因となるウイルスの一種で、主に冬季に流行します。非常に少量のウイルスでも感染が成立するほど強い感染力を持ち、集団生活の場では爆発的な感染拡大が起こることもあります。
感染者の便や吐物に含まれるウイルスが、手や口を介して体内に侵入し、腸管で増殖することで発症します。アルコール消毒が効きにくいため、対策には次亜塩素酸ナトリウムなどの適切な消毒が必要です。
感染源は、ウイルスに汚染された食品(特にカキなどの二枚貝)や、人との接触、家庭内での飛沫感染など多岐に渡ります。自覚症状がないまま周囲に感染させてしまうケースもあるため、予防と早期対応が重要です。
ノロウイルスの主な症状とは?
ノロウイルスに感染すると、突然の激しい症状が現れるのが特徴です。
主な症状は以下の通りです。
- 嘔吐
原因となる食品の摂取後、24〜48時間後に突然の吐き気や嘔吐症状で発症することが多く、1日に何度も繰り返す場合もあります。 - 下痢
水のような便(水様性下痢)が何度も出るのが特徴で、ひどい場合は1日に数十回もの下痢があり、脱水の原因となることもあります。 - 腹痛・腹部不快感
下痢とともに腹痛を訴える方もいます。痛みの程度は個人差がありますが、お臍の周りからみぞおちにかけての痛みや、下腹部の痛みが出るケースが多いです。 - 微熱
高熱になることは少なく、37〜38℃の微熱で済むことが一般的です。
発熱症状や嘔吐症状は比較的短期間で収まりますが、下痢や腹痛症状は長引く方もいらっしゃいます。
特に、体力が落ちている方や基礎疾患がある方では重症化する恐れもあり、注意が必要です。脱水症状を予防するためにも、症状が出た際はこまめな水分補給が重要です。
子ども・高齢者に多い特徴的な症状
ノロウイルスは年齢を問わず感染しますが、特に子どもや高齢者は免疫力が低いため、重症化しやすい傾向があります。そのため、3歳未満の乳幼児や65歳以上の高齢者に限り、ノロウイルス検査は保険適応となります。それ以外の患者様でも、検査をご希望の患者様は保険適用外の検査(自費検査)として検査を受けるが可能です。
子どもによく見られる症状
- 嘔吐が主症状となるケースが多く、突然何度も吐く
- 下痢が始まる前に嘔吐が先行することが多い
- 水分が取れず脱水症状を起こしやすい
高齢者によく見られる症状
- 発熱や倦怠感など、風邪のような症状から始まる
- 嘔吐物が喉に詰まって誤嚥性肺炎を起こすことがある
- 脱水により意識がぼんやりしたり、血圧が下がることがある
特に高齢者施設や保育園などでは集団感染が起こりやすいため、初期症状の見逃しには注意が必要です。
症状が出るまでの潜伏期間は?
ノロウイルスの潜伏期間は、感染から約24〜48時間(1〜2日)が一般的です。
ウイルスに触れた直後に症状が出るわけではなく、数日後に突然嘔吐や下痢などの症状が現れます。
また、感染源を特定する際にも、数日前まで遡って、何を食べたか、どこに行ったかなどを振り返ることが大切です。食事や行動歴を記録しておくと、感染源の特定や周囲への注意喚起に役立ちます。
症状の持続期間はどのくらい?いつまで感染力がある?
ノロウイルスによる症状は、通常1〜3日程度で自然におさまります。
嘔吐は1〜2日で治まることが多く、下痢はそれよりもやや長く続く場合があります。比較的短期間の経過ではありますが、脱水や体力低下に注意が必要です。
しかし、症状が治まった後も数日間は感染力が持続します。ウイルスは症状のピーク時に最も多く排出されますが、回復後も1週間程度は便中に排出され続けることが知られています。そのため、症状が治ったからといってすぐに安心せず、手洗いやトイレ後の衛生管理を継続することが大切です。
特に食品を扱う仕事に従事している方や、乳幼児・高齢者と接する機会がある方は、症状が治まっても数日は出勤・通園を控える配慮が求められます。
ノロウイルスの感染経路とは?家庭内感染に注意!
ノロウイルスは非常に感染力が強く、わずかなウイルス量で感染が成立します。
感染経路は主に以下の3つです。
経口感染(食品を介した感染)
ウイルスに汚染された食品、特に生のカキなどの二枚貝が原因となることがあります。
原因となる食品を加熱不十分で食べた場合はもちろんのこと、ノロウイルスに感染した人が調理した食品を食べた場合、感染者の手から食べ物にノロウイルスが付着し、二次的に感染する場合もあり、消費者側だけの注意では完全な予防が困難な場合もあります。
接触感染
感染者の便や吐物に直接触れた手にウイルスが付着することによって感染します。
また、感染者が手洗い不十分で触れた接触物を介して感染する場合もあります。
飛沫感染・空気感染
下痢や嘔吐物の飛沫や、それが乾燥して空気中に舞い上がったものを吸い込んで感染するケースもあります。
家庭内では、トイレの共有や嘔吐処理の際の不適切な対応が感染拡大の原因になります。タオルの共用やドアノブなどの接触感染にも注意が必要です。
家庭内に感染者が出た場合、嘔吐物や便の処理には塩素系消毒剤(次亜塩素酸ナトリウム)を使用することが効果的です。また、接触感染・飛沫感染・空気感染を避けるために、マスク・手袋・使い捨ての雑巾を使った処理なども有効です。
感染予防のポイント(手洗い・消毒・食事管理など)
ノロウイルスはアルコール消毒に強く、感染予防には正しい手洗いと環境消毒が重要です。日常生活で気をつけたいポイントは以下の通りです。
- 手洗いの徹底
調理前、食事前、トイレの後は、石けんを使ってしっかり手を洗いましょう。指先、爪の間、手首まで丁寧に洗うことが大切です。 - 消毒の工夫
アルコールは効果が弱いため、次亜塩素酸ナトリウム(家庭用漂白剤を薄めたもの)での消毒が有効です。特にトイレやドアノブ、嘔吐物の処理後は念入りに行いましょう。 - 食品の加熱
加熱不十分な二枚貝(特にカキ)は感染リスクが高いため、中心温度85〜90℃で90秒以上の加熱が推奨されます。
自宅での対処法|症状が出たときに気をつけること
ノロウイルスの治療は対症療法が基本です。ウイルスに直接効く薬はないため、自宅では以下の点に注意しながら安静に過ごしましょう。
- 脱水対策
嘔吐や下痢で失われた水分・電解質を補うために、経口補水液やスポーツドリンクを少しずつ、こまめに摂取することが重要です。 - 無理に食べない
吐き気や腹痛が強い場合は無理に食事をとらず、体調が落ち着いてからおかゆなどの消化に良い食事を少量ずつ始めましょう。 - 感染拡大の防止
嘔吐物や便の処理の際には手袋・マスクを使用し、使い捨てのペーパーで処理した後、塩素系消毒剤で消毒しましょう。衣類やリネン類は洗濯前に熱湯消毒すると効果的です。
病院に行くべき症状は?受診の目安と何科を受診するか
ノロウイルスは多くの場合、数日で自然に回復しますが、症状が重い場合や特定の状況では医療機関の受診が必要です。
以下のような場合は、早めに受診しましょう。
- 嘔吐や下痢が長引き、水分が摂れず脱水症状が出ている
- 高熱が続く、意識がぼんやりしている
- 乳幼児や高齢者で、ぐったりしている、尿が出ない
- 嘔吐物に血が混じっている、黒色便が出る
受診先は消化器内科が適しています。小児の場合は小児科を受診してください。
当院のような消化器を専門とするクリニックであれば、迅速な診断と必要に応じた点滴治療なども可能です(※ノロウイルスの迅速診断は多くの場合、保険適用外の自費検査となります)。
まとめ
ノロウイルスは非常に感染力が強く、突然の嘔吐や下痢などを引き起こすウイルス性胃腸炎の一種です。子どもや高齢者では症状が重くなることがあり、脱水症や誤嚥性肺炎などのリスクもあるため注意が必要です。
潜伏期間は1〜2日で、発症から数日で症状は治まりますが、ウイルスはしばらく体内に残り、便を通じて排出されるため、回復後も感染対策を続けることが重要です。
手洗い、消毒、食品の加熱など、日常的な予防を徹底し、万が一感染した場合でも周囲に広げないよう正しい知識を持って対応しましょう。重症化が疑われる場合は、速やかに医療機関を受診してください。