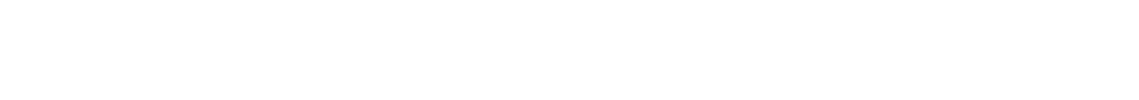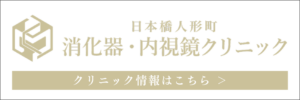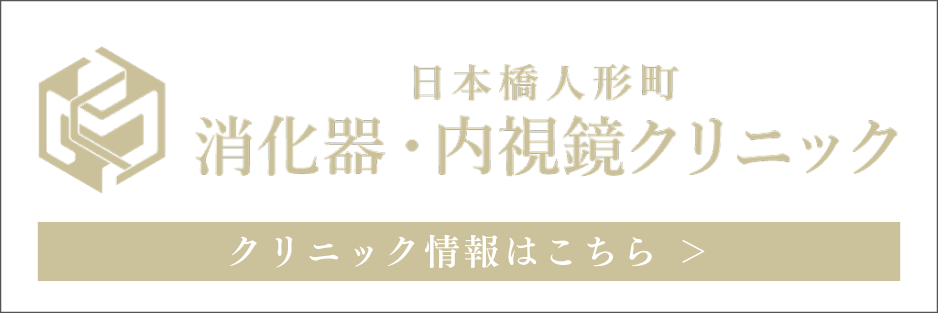2025年3月21日
「最近、胃もたれがひどい…」「胸やけがする…」「げっぷがよく出る…」
これらの症状は、もしかしたら食道裂孔ヘルニアが原因かもしれません。
食道裂孔ヘルニアは、軽度のものを含めると日本人の2人に1人が抱えていると言われている、とても身近な状態です。ネット記事などで「食道裂孔ヘルニアは治らない」などという記事を目にして心配されて来院される方も多いですが、実際のところはどうなのでしょうか。
この記事では、食道裂孔ヘルニアの症状や原因、治療法などをわかりやすく解説していきますので、ぜひ最後まで読んでみてください。

食道裂孔ヘルニアとはどんな状態?
食道裂孔ヘルニア(読み方:しょくどうれっこうへるにあ)とは、胃の一部が横隔膜の食道裂孔という穴から胸腔内に飛び出してしまった状態です。
横隔膜とは、呼吸をする際に重要な役割を果たす筋肉で、胸とお腹を隔てています。
この横隔膜には、食道が通るための「食道裂孔」と呼ばれる穴があります。何らかの原因でこの食道裂孔に緩みが生じ、本来は横隔膜の下の腹部にあるべき胃の一部が胸腔内に飛び出してしまった状態が食道裂孔ヘルニアです。
食道裂孔ヘルニアになると、胃酸など胃の内容物が食道に逆流しやすくなり、胸やけやげっぷ、胃もたれなどの症状が現れることがあります。
食道裂孔ヘルニアの種類
食道裂孔ヘルニアは、胃の一部が横隔膜の食道裂孔から胸腔内に飛び出す病気ですが、その飛び出し方によって、大きく3つの種類に分けられます。
1. 滑脱型食道裂孔ヘルニア
食道と胃の接合部が横隔膜の上方に移動した状態です。肥満や内臓脂肪の蓄積などによる腹圧の上昇や、加齢、姿勢の悪さなどによって起こりやすく、食道裂孔ヘルニアの90%以上を占めているといわれている、最も多いタイプです。軽度のものでは症状がないこともありますが、逆流性食道炎を伴うことも少なくありません。
2. 傍食道型食道裂孔ヘルニア
食道胃接合部のずれ込みはないものの、胃の一部が食道裂孔から飛び出し、食道と並んで胸腔内に存在するタイプです。 一般的には無症状ですが、嵌頓(かんとん)といって、飛び出した胃が食道裂孔にはまり込んで戻らなくなると、絞扼(締め付け)が起こるリスクがあります。 嵌頓・絞扼が起こると、激しい痛みや吐き気などの症状が現れ、緊急手術が必要になることもあります。
3. 混合型食道裂孔ヘルニア
滑脱型と傍食道型の両方の特徴を併せ持つタイプです。
食道裂孔ヘルニアの原因は?
食道裂孔ヘルニアの原因は、完全に解明されているわけではありませんが、一般的には以下の要因が関係していることが知られています。
- 加齢
加齢に伴い、横隔膜の筋肉が弱くなることが原因の一つです。 - 肥満
体重の増加により腹圧が上昇し、胃が押し上げられることで食道裂孔ヘルニアが発生しやすくなります。特に内臓脂肪が多い場合はリスクが高まります。 - 妊娠
妊娠中は、胎児の成長によって腹圧が上昇し、食道裂孔ヘルニアのリスクが高まります。 - 姿勢の悪さ
腰が曲がってくることにより横隔膜の変形や腹部が圧迫され、食道裂孔ヘルニアのリスクが高まります。以前は加齢に伴う腰曲がりが多かったものの、近年ではデスクワークやスマホ利用に伴い、若年者でも食道裂孔ヘルニアが見られる頻度が明らかに増えています。 - 重いものを持ち上げる
重いものを持ち上げるなど、腹圧が急激に上昇する動作も、食道裂孔ヘルニアの原因となることがあります。特にジムなどで重量系を扱う方や、力仕事の方に特徴的です。 - 便秘
便秘になると、排便時に強くいきむことで腹圧が上昇し、食道裂孔ヘルニアのリスクが高まります。 - 飲酒・喫煙
飲酒や喫煙は、横隔膜の筋肉を弛緩させ、食道裂孔ヘルニアのリスクを高めます。 - 高脂肪食
高脂肪食の摂取は、横隔膜の筋肉を弛緩させ、食道裂孔ヘルニアのリスクを高めます。食生活習慣の変化などにより、若年者の食道裂孔ヘルニアが増えていると言われています。
食道裂孔ヘルニアは痩せると治るか?
食道裂孔ヘルニアは、軽度のものであれば痩せることで症状が改善する可能性があります。
特に、肥満が原因で食道裂孔ヘルニアになっている場合は、体重を減らすことで腹圧が低下し、胃が食道裂孔から飛び出しにくくなるため、効果が期待できます。また、逆流性食道炎症状を伴っている場合、減量により約80%もの方が症状の軽減を実感するという研究結果もあり、症状を改善するための方法の一つとして、体重管理を行うことが大切です。食生活の見直しや適度な運動など、健康的な方法で体重を減らすように心がけましょう。
しかし、食道裂孔ヘルニアは加齢や生活習慣なども原因となるため、痩せただけで完全に治るとは限りません。また中等度以上の食道裂孔ヘルニアは、自然治癒は見込めないため、早い段階での対処が重要です。
食道裂孔ヘルニアの治療法
食道裂孔ヘルニアの治療法は、症状の程度や原因によって異なります。
軽症の場合は、生活習慣の改善や薬物療法が中心となります。
生活習慣の改善
適正体重の管理に努める、1回の食事量を少なくする、脂肪分の多い食事やアルコール、喫煙などを控える、腹圧を高めないようにする、締め付けの強い服装は避ける、食後すぐに横にならない、前かがみの姿勢を避けるなど、生活習慣を見直すことが大切です。
薬物療法
食道裂孔ヘルニアに伴い胃酸の逆流症状などを伴う場合は、胃酸の分泌を抑える薬や、食道粘膜を保護する薬などを使用します。食道内に溜まった胃酸の排泄を促す効果に期待して、胃の運動機能改善薬を併用する場合もあります。
これらの薬物療法でも症状をコントロールできない中等度以上の食道裂孔ヘルニア症例に対して、手術療法が検討されます。
手術療法
胃を適切な位置に戻し、食道裂孔を縫い縮める手術を行う場合があります。以前は、腹腔鏡手術が主流でしたが、近年ではより身体への負担が少なく、術後の回復も早い「内視鏡的噴門形成術(ARMS:Anti-reflux mucosectomy/ARMA:Anti-reflux mucosal ablation/ARM-P:endoscopic anti-reflux mucoplasty)」と呼ばれる手術が実施される例も増えています。いずれも限られた施設でのみ行なっている特殊な手術ですので、手術が必要な患者様は手術可能な高次医療機関へご紹介しています。
食道裂孔ヘルニアの予防
食道裂孔ヘルニアを完全に予防することは難しいですが、以下の点に注意することで、発症のリスクを減らすことができます。
- 肥満の解消
肥満は腹圧を高め、食道裂孔ヘルニアのリスクを高めるため、適正体重を維持することが大切です。バランスの取れた食事と適度な運動を心がけましょう。 - 食生活の改善
脂肪分の多い食事や、アルコールなどは、食道胃接合部を弛緩させ、食道裂孔ヘルニアを悪化させる可能性があります。これらの過度な摂取を控え、消化の良いものを食べるようにしましょう。また、早食いや夜食なども食堂裂孔ヘルニアのリスク因子となります。 - 腹圧をかけない
重いものを持ち上げたり、力んだりする際は、腹圧をかけすぎないように注意しましょう。また、便秘を予防することも大切です。 - 禁煙
喫煙は横隔膜の筋肉を弱めるため、食道裂孔ヘルニアのリスクを高めます。禁煙を心がけましょう。
よくある質問
Q. 食道裂孔ヘルニアは自然に治りますか?
A. 軽度の食道裂孔ヘルニアであれば、原因となる生活習慣等の改善によって治ることはありますが、中等度以上になると残念ながら、自然に治ることはありません。
そのため、早い段階から生活習慣の改善に取り組み、継続することが推奨されます。また、これにより食道裂孔ヘルニアに伴う逆流性食道炎の症状を和らげたり、進行を遅らせたりすることも可能です。症状が強い場合は、薬物療法など、適切な治療介入を行うことが望ましいため、お近くの消化器内科を受診してください。
Q. 食道裂孔ヘルニアと診断されましたが、手術は必要ですか?
A. 手術が必要となるのはごく一部の症例に限られます。
食道裂孔ヘルニアの治療法は、症状の程度や原因によって異なりますが、多くの場合は生活習慣の改善や薬物療法で症状をコントロールすることが可能です。
症状が重い場合や、薬物療法で効果がない場合は、手術が必要となることもあります。
Q. 食道裂孔ヘルニアは再発しますか?
A. 軽度の食道裂孔ヘルニアで生活習慣の改善等により症状改善した場合は、当然のことながら再発する可能性があります。手術を受けた場合は、手術の方法にもよりますが、再発は〜30%程度と報告されています。
いずれの場合も、再発を予防するためには、肥満の解消、食生活の改善、腹圧をかけない、姿勢を正す、禁煙など、日頃から生活習慣に気を配ることが大切です。
まとめ
食道裂孔ヘルニアは、胃の一部が横隔膜の食道裂孔から胸腔内に飛び出してしまう病気で、胸やけやげっぷ、胃もたれなどの症状を引き起こします。
原因は、加齢、肥満、妊娠、重いものを持ち上げる、便秘、猫背、喫煙など、さまざまな要因が考えられます。
痩せることで症状が改善する可能性はありますが、完全に治るわけではありません。
治療法としては、生活習慣の改善、薬物療法、手術療法などがあり、症状の程度や原因に合わせて適切な治療法を選択する必要があります。
食道裂孔ヘルニアは、日常生活に支障をきたす可能性のある病気です。
もし、食道裂孔ヘルニアが疑われる症状がある場合は、早めに医療機関を受診し、適切な診断と治療を受けるようにしましょう。