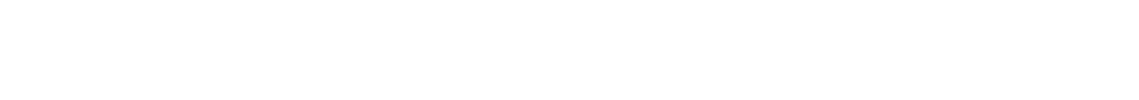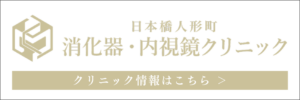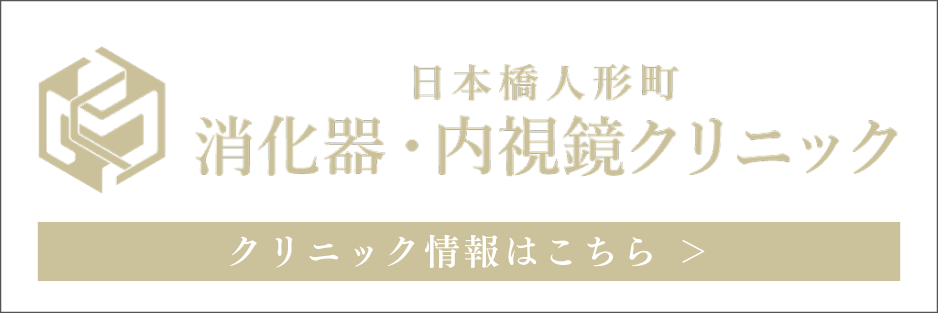2025年7月23日
「腸閉塞」と聞くと「まったく便が出ない」状態を想像される方も多いかもしれません。しかし、実際には便が出ていても腸閉塞だったというケースも存在します。
本記事では、腸閉塞でも便やガスが出る理由や、見逃してはいけない症状、受診の目安について、消化器内科専門医がわかりやすく解説します。

腸閉塞とは?
腸閉塞(ちょうへいそく)とは、腸の内容物の通過が何らかの原因によって物理的に妨げられ、腸内にガスや便、液体などが滞ってしまう状態を指します。
かつては「イレウス」という言葉で広く呼ばれていましたが、近年は用語の整理が進み、以下のように区別されています。
腸閉塞(従来の機械的イレウス)
腸閉塞の代表的な原因は、開腹術後の癒着です。癒着した腸管がねじれたり、腸管内がバンド状に締めつけられることで、通過障害が生じます。その他、腫瘍などにより、物理的に腸管がふさがれている状態も腸閉塞に該当します。
イレウス(従来の機能性イレウス)
腸管が麻痺し、蠕動運動が消失することで内容物が流れなくなる状態(炎症や手術後、血流障害などが原因)。
そのため、以前「絞扼性イレウス」と呼ばれていた病態は、現在では「絞扼性腸閉塞」と表現されるのが正確です。主な症状には、腹痛・吐き気・嘔吐・膨満感・排ガスや排便の停止などがあり、放置すると腸壊死や命にかかわることもあるため、早期の診断と治療が必要です。
腸閉塞でも便やガスが出ることはある?
「腸閉塞=便が全く出ない」というイメージを持たれがちですが、部分的な閉塞(不完全閉塞)では、腸閉塞でも排便や排ガスが一時的に見られることがあります。
また、発症初期には閉塞部位より手前(肛門側)にあった内容物が排出されることもあります。
以下のようなケースでは腸閉塞が進行していても排便・排ガスが見られる可能性があります。
-
発症直後で、腸内に残っていたガスや便が出ている段階
-
小腸閉塞で、大腸内に便が残存している場合
-
閉塞が不完全で、ある程度の通過が可能な状態
「便が出たから安心」と自己判断せず、その他の症状とあわせて総合的に判断することが重要です。
「便が出たから腸閉塞ではない」とは限らない理由
腸閉塞を疑う症状があるにもかかわらず、「便が出たから大丈夫」と自己判断してしまうのは非常に危険です。
腸閉塞では発症初期や閉塞位置によっては、ある程度の排便がみられることがあるため、便の有無だけでは診断できません。
理由としては、以下のような状況が考えられます。
-
閉塞部位より下流の腸内にあった便が一時的に排出された
-
小腸での閉塞では大腸に便が残っていることが多い
-
麻痺性イレウスで、腸の動きが断続的に回復・低下を繰り返している場合
こうした状況では、排便があっても、腹痛や嘔吐、膨満感などの他の症状も加味して評価する必要があります。
不完全な腸閉塞(部分閉塞)の特徴
腸閉塞には「完全閉塞」と「不完全閉塞(部分閉塞)」の2つがあり、不完全閉塞では腸の一部が狭くなっているものの、内容物がある程度通過できる状態です。
不完全な腸閉塞の主な特徴は以下のとおりです。
-
排便・排ガスがあるが、腹痛や吐き気が断続的に起こる
-
食後に腹部膨満感が強くなる
-
便秘や下痢を繰り返す
-
腸の動きに伴ってゴロゴロと音が鳴ることがある
-
症状が波のように現れては消える(間欠的)
こうした症状は、腸が狭窄している場所を無理に通ろうとして腸が過剰に動くことで生じます。ただし、排便や排ガスが見られることがある一方で、放置すれば完全閉塞に進行しうるため、症状が持続する場合には、早めに医師の診察を受けて原因を明らかにすることが重要です。
受診の目安|どんな症状があれば病院へ?
腸閉塞やイレウスは早期診断と適切な治療が鍵となります。
原因によっては、放置すると腸の壊死や腹膜炎を引き起こし、命に関わることがあります。以下のような症状がある場合には、速やかに医療機関を受診してください。
早めに受診すべき症状
-
繰り返す腹痛や膨満感
-
吐き気や嘔吐
-
ガスや便が出ない状態が続いている
-
強い腹部の張りや異常な音(腸雑音)
-
発熱や脱水症状(口の渇き、尿が出ない)
緊急受診が必要な症状
-
激しい腹痛が続く
-
繰り返す嘔吐でぐったりしている
-
血圧低下や意識の低下がある
-
高熱を伴う場合
とくに高齢者や基礎疾患のある方は、症状に気づきにくいこともあります。
少しでも不安があれば早めに受診することが予後の改善につながります。
腸閉塞の検査・治療方法
腸閉塞が疑われる場合、医療機関ではまず症状の聞き取りと身体診察が行われ、次いで以下のような検査によって診断が進められます。
主な検査方法
-
腹部X線検査
腸内にガスや液体が溜まっている様子を確認できます。「鏡面像」と呼ばれる典型的な所見が見られることがあります。
-
腹部CT検査
より詳しく腸の状態や閉塞の部位・原因を把握できます。腫瘍や癒着、腸管のねじれ(腸捻転)などの確認にも有効です。
-
血液検査
炎症の程度や脱水、腸の壊死リスクなどを確認します。
-
超音波検査(エコー)
特に高齢者や小児、妊婦に対して被ばくの少ない方法として有用です。
主な治療法
-
保存的治療(手術を行わない)
点滴による水分・電解質補正、絶食、経鼻小腸減圧チューブによる腸内容物の持続吸引などで腸の負担を減らします。軽度な癒着や一時的な機能低下などに有効です。
-
手術治療
腸のねじれなどによる血流障害や腸管壊死などがある場合は緊急手術が必要です。
絞扼(こうやく)を解除したり、壊死した腸管の切除が行われることもあります。また、腫瘍による閉塞の場合も同様に手術治療が必要となります。場合によっては一時的に人工肛門の造設や経肛門的減圧チューブ・腸管ステントなどによる減圧を行う場合もあります。
治療後の生活で気をつけたいこと
腸閉塞の中でも最も多い「腹部手術後の癒着」による腸閉塞
一度起こると再発のリスクも高くなります。再発を防ぐためには、まず日々の食事に注意が必要です。食事は少量ずつゆっくりと、よく噛んで食べることで腸への負担を減らし、内容物の通過をスムーズにします。また、便秘を放置せず、排便のリズムを整えることも大切です。加えて、漢方薬の「大建中湯」も再発予防目的によく処方されます。大建中湯は腸の血流を改善し、蠕動運動を促進する働きがあるとされており、癒着による腸閉塞の再発予防を目的に、術後や退院後に継続的に服用されるケースもあります。
大腸がんやクローン病など、腫瘍や慢性炎症性腸疾患が原因となる腸閉塞
根本疾患の管理が再発予防の鍵となります。特にクローン病などで腸管の狭窄がある場合は、繊維質の多い食事が腸に詰まりやすくなるため注意が必要です。必要に応じて、医師や栄養士の指導のもとで「低残渣食(ていざんさしょく)」に切り替えることも検討されます。また、定期的に内視鏡検査や画像検査を受けることで、腫瘍の再発や狭窄の進行を早期に把握することが可能です。炎症を抑える薬の継続や、腫瘍性病変に対する適切なフォローアップも含め、医療機関での定期的な管理が必要です。
腸の蠕動運動が一時的または持続的に低下してしまう「イレウス」
汎発性腹膜炎や術後、感染症、あるいは特定の薬剤(オピオイド系鎮痛薬、抗コリン薬など)が原因となることがあります。このタイプの腸閉塞では、まず原因となる疾患や薬剤の管理が不可欠です。たとえば糖尿病や腎機能障害が背景にある場合は、それらの病気を適切にコントロールすることで腸の機能も安定しやすくなります。また、脱水が腸の動きを悪化させることがあるため、水分はこまめにとるようにしましょう。薬の副作用が疑われる場合には、自己判断で服薬を中止せず、医師に相談することが重要です。
すべての腸閉塞の原因に共通して言えることは、「腸に過度な負担をかけない生活」を意識することです。規則正しい生活とバランスのとれた食事を心がけ、便秘やお腹の張りなどの症状が続く場合には早めに医療機関を受診することが大切です。また、軽いウォーキングやストレッチなどの無理のない運動も、腸の動きを促進する助けになります。腸閉塞は再発しやすい疾患のひとつです。退院後も継続的に医療機関での経過観察を行い、体調の変化を見逃さないことが大切です。
まとめ
腸閉塞は、便やガスが出ているからといって安心できる病気ではありません。
不完全閉塞や発症初期には腸内に残っていた内容物が排出されることもあるため、「便が出た=腸閉塞ではない」とは限らないのです。
以下のような症状がある場合は、腸閉塞やイレウスの可能性があります。
-
強い腹痛や腹部の張り
-
吐き気や嘔吐
-
排便・排ガスの異常
-
発熱や脱水症状
特に高齢者や基礎疾患がある方では、症状に乏しいこともあるため注意が必要です。医療機関を受診し、画像検査などを通じて原因を特定することが、重篤化を防ぐ第一歩です。また、腸閉塞は治療後も再発のリスクがあるため、生活習慣や食事にも気を配り、定期的な受診を心がけましょう。
よくある質問
便秘は大腸内の便が滞って排出されにくくなる状態です。一方で、腸閉塞は腸管の物理的または機能的な異常により、ガスや内容物の通貨が傷害される病態です。腸閉塞では腹痛・嘔吐・腹部の張りなど全身症状を伴いやすく、早期の医療介入が必要です。
なお、便そのものが腸に詰まって通過を妨げる「糞便性腸閉塞」と呼ばれる状態もあります。これは重度の便秘が原因で腸閉塞を引き起こすタイプであり、便秘が進行すると腸閉塞に発展することもあるため、長期間の排便困難や腹部症状には注意が必要です。つまり、便秘と腸閉塞は異なる病態ですが、両者が連続性を持って進行するケースもあることを理解し、早めに医療機関で診断を受けることが重要です。
あります。特に手術後の癒着が原因となる場合、再発リスクが高くなります。再発予防には、食事の工夫・便通のコントロール・定期的な医師のフォローが重要です。
市販薬での改善は期待できません。特に誤って下剤を使用すると、かえって状態を悪化させる可能性もあります。腸閉塞が疑われる場合は、自己判断せず必ず医療機関を受診してください。
軽度の(機能性)イレウスや、術後癒着の不完全閉塞では絶食安静等により一時的に腸の動きが回復することもあります。ただし、完全閉塞や絞扼性腸閉塞では緊急手術が必要になるケースもあり、放置は非常に危険です。特に痛みや嘔吐、膨満感などの症状がある場合は、必ず医療機関を受診し、専門的な判断を仰ぐ必要があります。
以下のような方は腸閉塞になりやすい傾向があります。
-
腹部の手術歴がある(癒着のリスク)
-
高齢者で腸の動きが弱くなっている、持病がある
-
腸に腫瘍や炎症性疾患がある(大腸がん、クローン病など)
-
食物繊維の過剰摂取や、よく噛まずに食べる習慣がある 日頃から便通を整え、腹痛やお腹の張りに注意することが予防につながります。