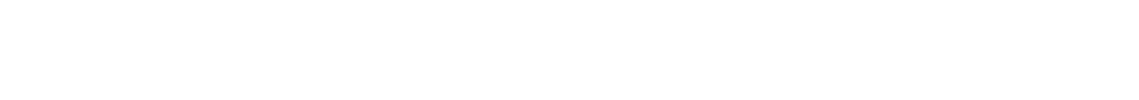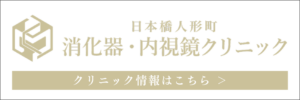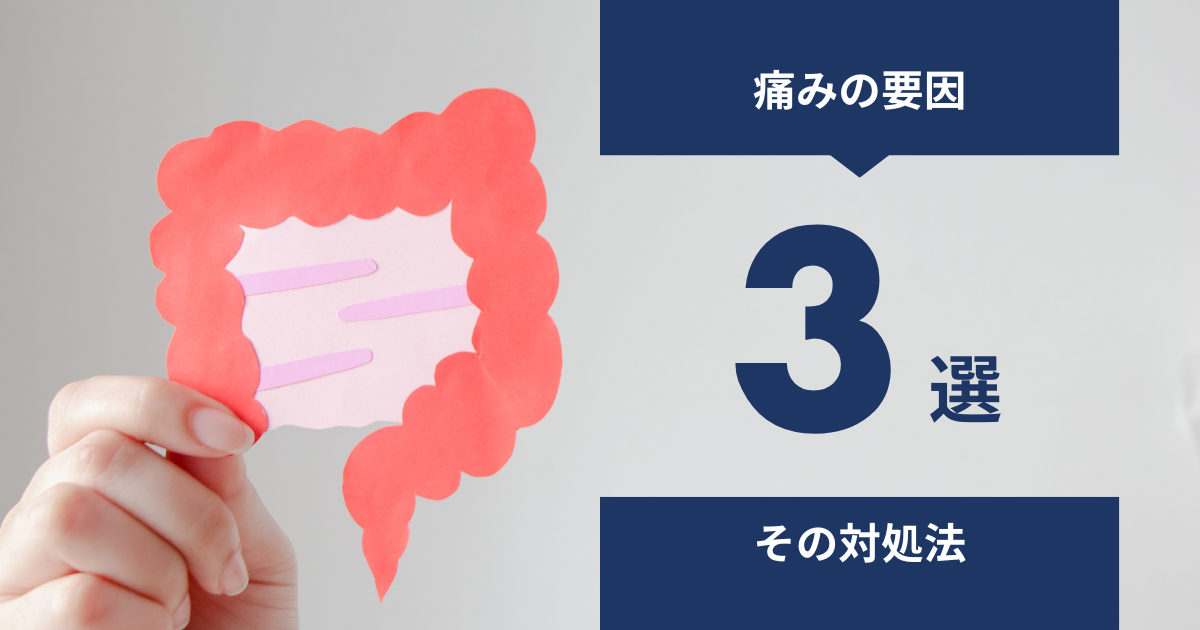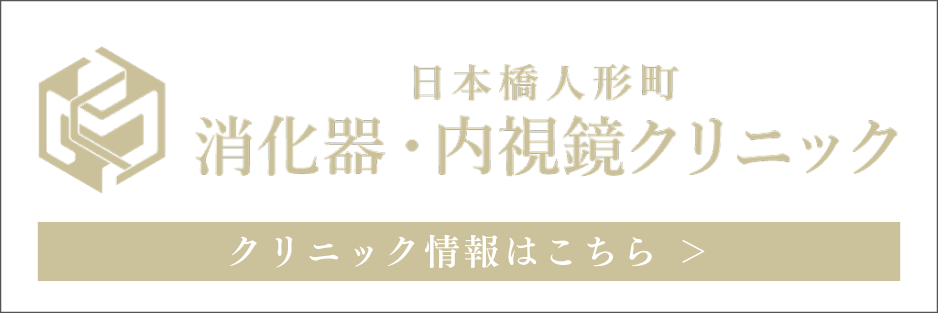2025年11月25日
大腸カメラ検査は「恥ずかしい」「痛そう」と感じて、検査をためらう方も多いのではないでしょうか。
そのような不安をお持ちの方に知っていただきたいのが「大腸CT検査」です。
大腸CT検査は、体への負担が少なく、短時間で大腸全体を調べられる検査方法です。内視鏡のように長いスコープを腸の奥まで挿入する必要がないため、痛みや苦しさを感じにくいのが特徴です(注:肛門から数cmほど細いチューブを挿入して炭酸ガスを注入するため、一時的なお腹の張り感や違和感はあります)。
この記事では、大腸CT検査がどんな検査なのか、何がわかるのか、費用はいくらか、内視鏡検査との違いなどをわかりやすく解説します。

大腸CT検査とは
大腸CT検査は、正式には「CTコロノグラフィー」と呼ばれる検査方法です。
内視鏡を使わずに、CT装置で大腸を撮影し、コンピューターで立体的な画像を作って大腸の状態を調べます。
検査の仕組み
前日に少量の下剤を服用したり、腸管内の残渣を見分けやすくするための造影剤(経口造影剤)を服用します。
検査では、肛門から細くて柔らかいチューブを数センチだけ入れます。
そこから炭酸ガスを注入して大腸を膨らませ、鎮痙薬を用い腸の動きを穏やかにした状態でCT撮影を行います。
撮影した画像を専用のコンピューターで処理すると、内視鏡で中を覗いているような立体画像で観察できます。
撮影自体は短時間で終わり、検査全体も短時間で完了します。
どんな時に選ばれるか
-
便潜血検査で陽性が出た方で、全大腸内視鏡検査を行うことが困難な方
-
過去の手術で腸に癒着があり、内視鏡が奥まで届きにくい方
-
大腸が長く、内視鏡が最後まで挿入できなかった方
-
高齢や併存疾患などで「全大腸内視鏡検査のリスクが高い」と医師が判断した方
ただし、大腸CT検査はこの検査だけで確定診断ができるわけではありません。
異常が見つかった場合は、診断確定やポリープ切除のために原則として大腸内視鏡検査が必要になります。
また、便潜血検査陽性者への精密検査として、大腸内視鏡検査を第一選択とするガイドラインがあり、大腸CTは「内視鏡が困難・拒否された場合の代替」として位置づけられています。
大腸CT検査でわかること
大腸CT検査では、主に次のような病変を見つけることができます。
-
大腸がん
-
大腸ポリープ
-
大腸憩室
-
大腸の炎症や狭窄
特に、6mm以上のポリープや大腸がんなど、ある程度の大きさと隆起性のある病変の発見においては、経験のある施設では高い感度(おおむね80〜90%以上)が報告されています。
一方で、平坦な病変や5mm未満の小さなポリープは、内視鏡検査と比べて見つけにくいことが知られています。
炎症性腸疾患(潰瘍性大腸炎など)の活動性評価やごく浅い表面変化の評価には、大腸CT検査単独では不十分な場合が多く、内視鏡検査や生検が必要になります。
大腸CT検査のメリット・デメリット
メリット
体への負担が少ない
内視鏡を入れないため、多くの方で痛みや苦しさを感じにくい検査です。(注:炭酸ガスで腸を膨らませるため、一時的にお腹の張りや違和感を自覚する場合があります。)
前処置としての下剤の量は、撮影技術や造影剤タギングの工夫により、大腸内視鏡検査よりも少ない量で行える場合も多いです。
検査時間が短く、終わったらすぐに日常生活に戻れます。
また、過去の手術で腸に癒着がある方や、腸が長くて内視鏡が入りにくい方でも検査が可能です。
大腸以外もチェック可能
大腸CT検査は、大腸だけでなくお腹全体を撮影できます。
大腸以外の臓器はあくまで「付随して写る範囲」であり、全身のがん検診を保証するものではありませんが、偶発的に大腸以外の病気が見つかることもあります。
デメリット
-
組織を採取できない
ポリープが見つかっても、その場で切除することはできません。異常があれば、改めて大腸内視鏡検査を受ける必要があります。
-
放射線被ばくがある
大腸CT検査ではX線を用いるため、一定量の放射線被ばくがあります。通常の1回の検査で大きな健康被害が出るレベルではありませんが、若年者や繰り返し検査を受ける方では、被ばく量を考慮する必要があります。
-
妊娠中の方や妊娠の可能性がある方は検査を受けられません。
妊娠中の方や妊娠の可能性がある方は、お腹の赤ちゃんへの放射線被ばくを避けるため、原則として検査を行いません。
-
高度な腸の炎症がある場合には行えないことがある
激しい炎症や重症の大腸炎がある場合、腸を膨らませる操作によって穿孔リスクが上がるおそれがあるため、大腸CT検査が選択されないことがあります。
大腸CT検査の費用
大腸CT検査は、人間ドックや健康診断のオプションとして「自費(自由診療)」で行われることが多い検査です。
一部のケースでは健康保険が適用されることもありますが、現状では 「限られた条件下でのみ保険適用が認められる検査」 と考えておくとよいでしょう。
自費の場合(人間ドック・健診など)
健康診断や人間ドックなど、検診目的で受ける場合は全額自己負担となります。
費用は医療機関によって異なりますが、2万円から3万円程度としている施設が多い印象です。
実際の料金は各医療機関にご確認ください。
保険適用の場合
医師が「診断上必要」と判断した場合 には、条件を満たせば健康保険の適用を検討できることがあります。
この場合、3割負担で数千円〜1万円台前半程度が一般的な費用です。
ただし、すべての医療機関で保険適用の大腸CT検査を実施しているわけではないことや、条件を満たしていても、施設の運用方針によっては自費のみとしている場合もあるため、「自分の場合に保険が使えるかどうか」 は、実際に検査を行う医療機関に事前に確認することをおすすめします。
当院での大腸CT検査の位置づけ(当院では原則として実施していません)
当院では、最新のガイドラインに則り、大腸内視鏡検査(大腸カメラ)を大腸検査の「ゴールドスタンダード」として位置づけています。
便潜血検査で陽性になった方や、大腸がん・大腸ポリープが疑われる方の精密検査としては、原則として全大腸内視鏡検査を第一選択としています。
その理由は、主に次の3点です。
-
ガイドライン上も、大腸内視鏡が精密検査の標準だから
日本を含む多くのガイドラインで、便潜血検査陽性者の精密検査としては「全大腸内視鏡検査」が基本となっており、大腸CT検査(CTコロノグラフィー)は「内視鏡がどうしても難しい場合の代替・補完」として扱われています。
-
当院では「他院で挿入困難と言われたケース」にも、できる限り対応しているから
以前に「大腸カメラが奥まで入らなかった」「他院で挿入困難と言われた」といった方でも、事前の診察でリスクや腸の状態を確認したうえで内視鏡の種類や挿入方法を工夫することで多くの場合、全大腸内視鏡検査を行うことが可能です。
-
結局、病気が見つかった場合は「大腸カメラが必要」になるため
大腸CT検査でポリープや大腸がんを疑う所見が見つかった場合、病変を詳しく観察するため、ないしは必要であれば組織採取やポリープを切除するため、最終的には 大腸内視鏡検査を追加で行う必要があります。
そのため当院では、「最初から大腸内視鏡検査を行い、必要に応じて同日中にポリープ切除まで行う」という方針を基本としており、患者さんの負担(検査回数や前処置の手間)をできるだけ少なくすることを重視しています。
以上のような理由から、当院では院内での大腸CT検査は原則として行っておりません。
どうしても大腸CT検査が必要と判断される特殊なケースでは、高次医療機関への紹介などで対応する場合がありますが、通常は 大腸内視鏡検査を中心とした診療を行っています。
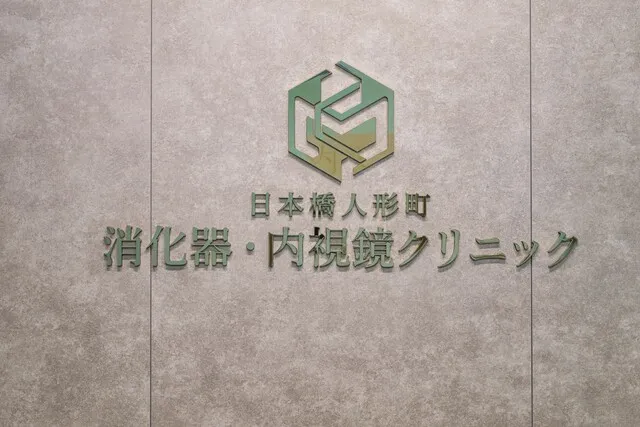
大腸内視鏡検査との比較
大腸CT検査と大腸内視鏡検査、どちらを選べばよいか迷う方も多いでしょう。
それぞれの特徴を比較してご説明します。
| 大腸CT検査 | 大腸カメラ検査 | |
| 体への負担 | ・痛みや苦しさが少ない方が多い ・検査時間が短い ・鎮静剤を使わないことが多い | 多少の不快感を伴うことがあります。 ただし、鎮静剤を使用すれば、眠っている間にほとんど苦痛なく検査を終えられます。 |
| 検査の精度 | 6mm以上の隆起性病変に対しては高い感度が報告されていますが、平坦な病変や5mm未満の小さなポリープは見つけにくいことがあります。 | 大腸の中を直接観察できるため、平坦病変を含め小さな病変も詳細に観察できます。 必要に応じて拡大観察や特殊光を用いた精密検査も可能です。 |
| 治療 | 画像診断のみで、組織採取やポリープ切除はできません。 異常が見つかれば改めて大腸内視鏡検査を受ける必要があります。 | ポリープが見つかれば、その場で切除したり、組織を採取して病理検査に回すことができます。 多くの場合、「検査と治療を同日に完了できる」点が大きな利点です。 |
| 放射線被ばく | 被ばくあり | 被ばくなし |
| 検診での位置づけ | 便潜血検査陽性者の精密検査として「全大腸内視鏡検査が第一選択」であり、内視鏡が困難・拒否された場合の代替として位置づけられています。 | 便潜血検査陽性者の精密検査として推奨される標準的な検査です。 |
大腸CT検査の流れ
検査前日
消化の良い食事を食べてください。
夕方から就寝前にかけて、下剤と少量の造影剤を飲みます。
前処置としての下剤の量は、大腸内視鏡検査よりも少ない量で行える場合も多いです。
検査当日
-
来院後、検査着に着替えます。
-
検査室では、まず肛門から細くて柔らかいチューブを数センチだけ挿入します。
そこから炭酸ガスをゆっくり注入して、大腸を膨らませます。 -
CT撮影を行います。
撮影は各体位で数十秒程度です。 -
撮影が終わったら、チューブからガスを抜いて終了です。
検査時間
検査室に入ってから出るまで、全体で15分程度で終わります。
検査後は、炭酸ガスが体に吸収されるため、お腹の張りも徐々に軽くなります。食事制限もありませんので、すぐに日常生活に戻れます。
注:鎮静剤は通常用いませんが、鎮痙薬を使用した場合には、当日の車の運転を控えるよう指示されることがあります。医療機関の指示に従ってください。
まとめ
大腸CT検査(CTコロノグラフィー)は、長い内視鏡スコープを使わずに、大腸の内側を立体画像として確認できる検査です。
検査時間が比較的短く、鎮静剤なしで行えることが多い一方、放射線被ばくがあることや、平らな病変・ごく小さなポリープは見つけにくいという限界があります。
日本のガイドラインでは、便潜血陽性時などの精密検査としては全大腸内視鏡検査(大腸カメラ)が標準検査(ゴールドスタンダード)であり、大腸CT検査は「内視鏡がどうしても難しい場合の代替・補完」と位置づけられています。
さらに、大腸CTで病変が疑われた場合も、確定診断やポリープ切除には結局大腸内視鏡検査が必要です。
当院ではこの考え方に基づき、他院で「挿入困難」と言われたケースも含め、可能なかぎり最初から大腸内視鏡検査で評価し、その日のうちにポリープ切除まで完了させる方針をとっています(そのため大腸CT検査は原則行っていません)。
「検査が不安」「前回つらかった」など気になる点があれば、自己判断で先延ばしにせず、まずは一度ご相談ください。
よくある質問
CT画像の解析には時間がかかるため、検査当日に結果が出ることは少なく、後日の説明となることが一般的です。異常が見つかった場合は、内視鏡検査での精密検査をお勧めされることがあります。
ガイドラインでは 「大腸CTを一定間隔で繰り返すこと」を大腸がん検診の標準と位置づけてはいませんが、検査の頻度については、検査結果や年齢、リスク要因などを考慮して医師と相談して決めることが大切です。
いいえ、確定診断はできません。大腸CT検査は画像検査のため、組織を採取して調べることができません。異常が見つかった場合は、内視鏡検査で組織を採取し、病理検査で確定診断を行う必要があります。
はい、可能です。鎮静剤を使用しないため、検査後すぐに日常生活に戻れます。車の運転もできますし、そのまま仕事に向かう方もいます。