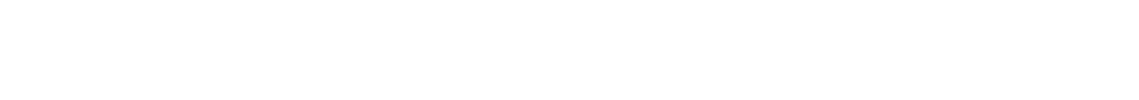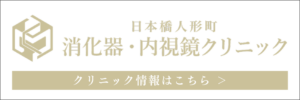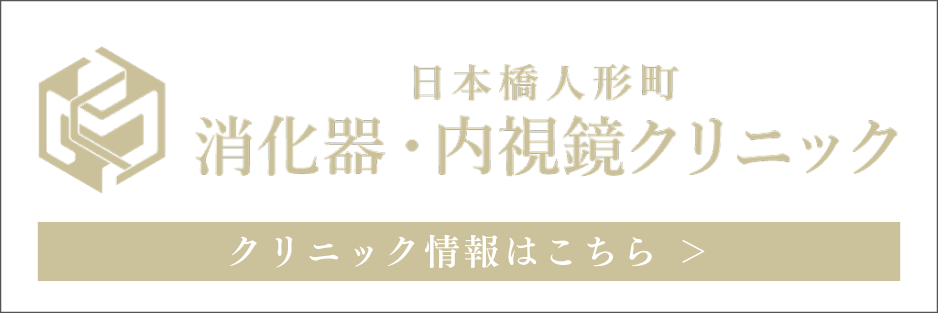2025年9月16日
薬を飲んだ後に胸の痛みや違和感を感じたことはありませんか。薬剤性食道炎(サプリメント潰瘍)は、錠剤やカプセルが食道に長くとどまり、粘膜を直接刺激したり、付着した薬剤による化学熱傷により起こる病気です。特にビタミン剤などのサプリメントや抗生物質、消炎鎮痛剤(NSAIDs)、骨粗鬆症治療薬などが原因となります。症状を放置すると食道狭窄や出血につながることもあるため、早めの対応が大切です。
本記事では、薬剤性食道炎の原因や治療法、受診の目安をわかりやすく解説します。

薬剤性食道炎とは?
薬剤性食道炎とは、内服薬やサプリメントが原因で食道の粘膜に炎症や潰瘍が生じる疾患です。
薬が食道に一時的に停滞し、その成分による化学熱傷や、浸透圧性の刺激、直接的なバリア機能障害などによる食道刺激で起こります。胃や腸の粘膜と異なり、食道の粘膜は物理的な刺激には強いものの、化学的な刺激には弱いため、炎症や傷ができやすい特徴があります。
代表的な原因薬には、抗生物質(テトラサイクリン系)、消炎鎮痛薬(NSAIDs)、鉄剤、ビタミン剤、骨粗鬆症治療薬などがあります。また、近年では健康補助食品やサプリメントでも同様の症状を引き起こすことが報告されています。
発症の背景には、「薬を水なし(もしくは少ない水)で飲む」「薬を飲んだ直後に横になる」などの生活習慣が関わることが多く、誰にでも起こりうる身近な病気といえます。
薬剤性食道炎の症状
薬剤性食道炎では、薬を飲んでから数時間〜数日以内に症状が現れることが多くあります。
主な症状は以下の通りです。
-
胸の中央あたりの痛みや焼けるような感覚
-
飲み込み時のつかえ感やしみるような痛み
-
のどや胸に薬が引っかかっているような違和感
-
胃酸の逆流に似た胸やけ
-
時に血の混じった唾液や吐血
症状は軽度で自然に改善することもありますが、悪化すると潰瘍を形成し強い症状を出したり、食道狭窄や出血を起こすこともあり注意が必要です。特に強い症状で経口摂取が難しい場合や、症状が長引く場合は、放置せず医療機関を受診してください。早期に診断・治療を行えば重症化を防ぐことができます。
薬剤性食道炎の原因
薬剤性食道炎は、薬そのものの性質と服薬時の習慣が重なって発症します。
薬の種類だけでなく飲み方や体質が組み合わさることで、食道に薬が停滞し炎症を引き起こします。
薬の性質による刺激
-
抗生物質(テトラサイクリン系)
-
消炎鎮痛薬(NSAIDs)
-
鉄剤やカリウム製剤
-
ビタミン剤、骨粗鬆症治療薬
-
サプリメント(特にカプセルタイプや大きな錠剤)
服薬方法の問題
-
水をほとんど飲まずに薬を服用した
-
寝る直前に薬を飲んで、そのまま横になった
-
座位や立位ではなく、寝た姿勢で服薬した
体質や背景
-
高齢で食道の動きが弱っている
-
唾液分泌が少ない
-
食道に狭窄や動きの異常がある
薬剤性食道炎の治療法
薬剤性食道炎の治療は、原因となる薬の中止や変更と、食道粘膜の炎症を和らげる治療が中心となります。
-
原因となっている薬を中止または別の薬に変更する
炎症を起こしている薬をまず止めます。医師の指示に従って、自分で勝手に薬をやめるのは避けましょう。場合によっては、似た効果があり、食道に負担のかからない別の薬に替えられます。
-
胃酸分泌を抑える薬を使う
食道の炎症を悪化させる胃酸の量を減らすため、「プロトンポンプ阻害薬(PPI)」や「H2ブロッカー」と呼ばれる薬を飲みます。これにより食道の粘膜が修復されやすくなり、痛みや胸やけが軽減します。
-
粘膜を保護する薬を使う
炎症を抑え、粘膜を守るための薬が処方されることもあります。これらは食道の傷を早く治す助けになります。
-
服薬方法の改善
薬を飲むときは、200ml程度のたっぷりの水でゆっくり飲みます。薬を飲んだ後は、少なくとも30分間は横にならず、身体を起こしたままでいることが大事です。これで薬が食道に留まるのを防げます。
-
生活習慣の見直し
刺激の強い辛い食べ物や酸味の強い飲み物を避け、やわらかく消化の良い食事を心がけましょう。禁煙や適度な運動も役立ちます。
多くは数日から数週間で改善しますが、潰瘍が深い場合や狭窄により拡張術が必要な場合、出血が強い場合は内視鏡での確認や処置、入院治療が必要になることもあります。
薬剤性食道炎は何科を受診する?
薬剤性食道炎が疑われる場合は、消化器内科の受診がおすすめです。
消化器内科では、胃カメラ(上部消化管内視鏡検査)を用いて食道の炎症や潰瘍の有無を詳しく確認できます。特に「薬を飲むと胸が痛む」「飲み込みにくさが続く」「吐血や血の混じった唾液が出る」といった症状がある場合は、早急な受診が必要です。
また、かかりつけ医がいる場合は、まず相談してから専門医に紹介してもらう流れも良いでしょう。原因となる薬の調整や代替薬の検討は、処方医と連携しながら進めることが大切です。自己判断で服薬を中止するのではなく、必ず医師に相談するようにしてください。
まとめ
薬剤性食道炎(サプリメント潰瘍)は、薬やサプリメントが食道に停滞して粘膜を傷つけることで起こる病気です。胸の痛みや飲み込み時の違和感など、日常生活に支障をきたす症状を引き起こすことがあります。
原因となる薬の種類や飲み方の工夫によって予防が可能であり、治療は薬の調整と粘膜保護、胃酸抑制薬などが中心です。大切なのは、薬は必ず十分な水で服用し、飲んだ直後に横にならないことです。
症状が出た場合には、自己判断せずに消化器内科を受診しましょう。早期に対応することで、潰瘍や出血などの重症化を防ぐことができます。
よくある質問
軽症であれば数日〜1週間ほどで自然に改善することもありますが、潰瘍や強い痛みがある場合は治療が必要です。
はい。特に大きなカプセルや鉄・ビタミン製剤などで発症することがあります。
一時的に胃薬で和らぐこともありますが、根本的な改善には医師の診断が必要です。
コップ1杯以上の水で服薬し、服薬後30分は横にならないようにしましょう。
消化器内科での診察がおすすめです。必要に応じて胃カメラ検査を行い、炎症や潰瘍の有無を確認できます。