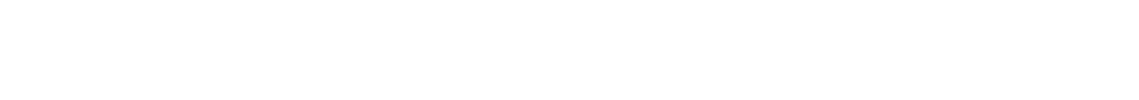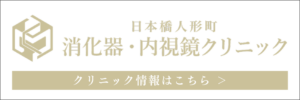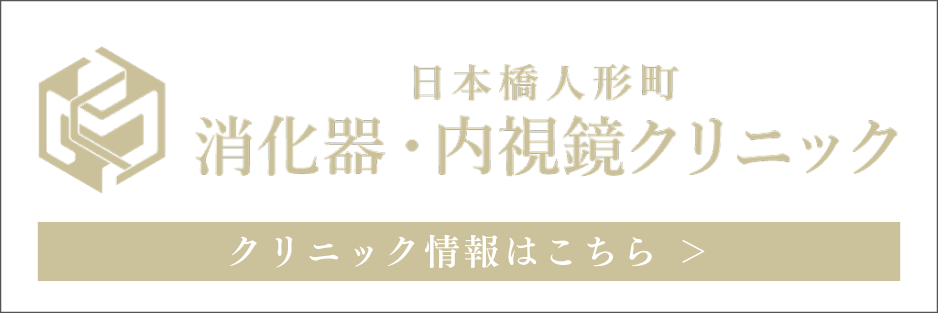2025年3月24日
様々なダイエット方法が流行してはなくなっていきますが、その中には健康を害する可能性のあるものも潜んでいます。その一つに「下剤ダイエット」があります。
この記事では、下剤ダイエットのリスクについて、日本消化器病学会専門医の立場から詳しく解説するとともに、下剤の正しい使い方についてもお伝えします。

下剤ダイエットとは?
下剤ダイエットとは、その名の通り、下剤を用いて体重を減らそうとする方法ですが、これはとても危険なダイエット方法です。
下剤を服用することで、腸の動きが活発になり、排便が促されるため、一時的に体重が減ることがあります。これは体内の水分や食べたものが排出されることによるものであり、脂肪が減るわけではありません。そのため、根本的なダイエット方法とは言えず、継続的な体重減少にはつながりません。
下剤は、あくまで便秘の治療薬であり、ダイエットのために使用されるべきものではありません。また、安易な使用を続けることで、健康を損なう危険性があり、注意が必要です。
下剤ダイエットの効果とリスク
下剤ダイエットは、一時的に体重が減少するように見えるかもしれませんが、それは体内の水分や便が排出されたことによるもので、体脂肪が減ったわけではありません。むしろ、下剤の乱用は、健康を害するリスクの方がはるかに大きいと言えます。
下剤ダイエットのリスクとして、以下のようなものが挙げられます。
- 脱水症状
下剤の使用によって、体内の水分が過剰に排出され、脱水症状を引き起こす可能性があります。 - 電解質異常
水分とともに、ナトリウムやカリウムなどの電解質も失われ、電解質異常を引き起こす可能性があります。これにより、筋肉のけいれんや不整脈のリスクも高まります。 - 腸内環境の悪化
誤った方法での下剤の常用は、腸内細菌のバランスを崩し、腸内環境を悪化させる可能性があります。 - 便秘の悪化
刺激性の下剤に頼り続けると、腸の動きが鈍くなり、かえって便秘が悪化する可能性があります。 - 依存性・薬剤耐性
刺激性の下剤の使用を続けると、腸が下剤の刺激に慣れてしまい、自然な排便が難しくなる「下剤依存症」になる危険性もあります。また、下剤の効きが悪くなる薬剤耐性を起こす場合もあります。
これらのリスクを考えると、下剤ダイエットは決して行うべきではありません。
下剤ダイエットの間違った認識
下剤ダイエットを試みる方の多くは、体重をとにかく減らしたい、と考えている方が多いです。
確かに、便の重量は体重に影響しますが、便は、主に食べ物のカスや腸内細菌、水分などから構成されており、体脂肪は含まれていません。下剤を使用することで、一時的に見かけ上の体重は減りますが、それはあくまで体内の水分や便が排出されたことによるものであり、体脂肪が減り痩せたわけではありません。
むしろ、下剤の乱用によって体内の水分や電解質が失われると、基礎代謝が低下し、体脂肪が燃焼しにくい状態になる可能性もあります。
そのため、長期的に見ると下剤ダイエットは体重減量には逆効果であり、健康を害するリスクもあることを理解しておく必要があります。
正しいダイエットとは、無理なく続けられる食事管理と適度な運動を組み合わせ、健康を維持しながら適正体重を目指すこと。下剤はそのための手段ではなく、あくまで便秘の治療薬であることを忘れてはなりません。
下剤の正しい使い方
下剤は、正しく使用すれば、便秘の症状を改善する有効な薬です。
しかし、自己判断で安易に使用することは避け、必ず医師や薬剤師に相談の上、用法用量を守って使用することが大切です。
便秘の治療のファーストステップは、食物繊維や水分をしっかり摂る、適度な運動をするなど、生活習慣の改善が大切です。一時的な便秘症状は生活習慣の改善だけでも、改善されることも少なくありません。
生活習慣の改善で効果が見られない場合は、下剤を使用することもありますが、下剤には、便を柔らかくして排便を促すものや、腸の動きを活発にしてスムーズに出しやすくするものなど、さまざまなタイプがあります。それぞれ作用機序や効果、副作用が異なり、便秘の種類や症状、体質に合わせて、適切な種類と用量を選択する必要があります。
市販薬も多くありますが、長期間の使用や自己判断での服用は、腸の機能が低下したり、依存性が生じたりすることがあるため注意が必要です。必要に応じて、医師や薬剤師に相談しましょう。
下剤を使用する際の注意点
- 自己判断で下剤を使用しない。
- 医師の指示に従って、適切な種類と用量を使用する。
- 下剤の種類や作用、副作用について、医師や薬剤師に十分な説明を受ける。
- 下剤の使用中に、体に異常を感じたら、すぐに医師に相談する。
市販の下剤薬を使用し続けると
ドラッグストアなどで手軽に購入できる市販の下剤薬。
便秘で悩んでいる方にとっては、手軽に症状を改善できる便利な薬ですが、安易な使用には注意が必要です。
市販の下剤薬の7〜8割は刺激性の下剤で、これらの下剤を自己判断で長期間使用し続けると、以下のような問題が起こる可能性があります。
大腸メラノーシス
刺激性下剤の長期使用により、大腸の粘膜が黒っぽく変色する状態を指します。これは大腸メラノーシスと呼ばれ、それ自体に症状はありませんが、腸の動きが鈍くなり、かえって便秘がひどくなることがあります。
薬剤耐性
刺激性下剤を頻繁に使用すると、腸が外部からの刺激に慣れてしまい、本来の蠕動運動が鈍くなります。その結果、下剤なしでは便が出にくくなり、使用量を増やさないと効果を感じにくくなります。週1~2回までにするなど、使用回数を制限することや、浸透圧性下剤(酸化マグネシウムなど)、腸への負担が少なく、耐性ができにくい薬剤への切り替えを検討することが重要です。
電解質異常
酸化マグネシウムは、浸透圧性下剤の一種で、腸内に水分を引き込み、便を柔らかくして排便を促す作用があります。刺激性下剤と違い、腸を直接刺激しないため、長期使用でも比較的安全とされています。
酸化マグネシウムを長期間・大量に使用すると、体内のマグネシウム濃度が上昇し、電解質のバランスが崩れることがあります。特に、腎機能が低下している人や高齢者では注意が必要です。
下剤は、正しく使用すれば、便秘の症状を改善する有効な薬ですが、誤った使い方をすると、健康を害する可能性もあります。下剤を使用する際は、必ず医師や薬剤師に相談し、指示に従うようにしましょう。当院では慢性便秘にお悩みの方のために便秘外来をおこなっておりますので、便秘にお困りの方はお気軽にご相談ください。
よくある質問
Q. 下剤を飲んでも便秘が改善しません。どうすればよいですか?
A. 下剤の種類や量、服用方法などが適切でない可能性があります。自己判断で下剤を服用し続けるのではなく、医療機関を受診し、医師に相談することをお勧めします。
Q. 便秘薬(下剤)を毎日飲んでも大丈夫ですか?
A. 便秘薬の種類やあなたの体質によって異なります。
一般的に、刺激性下剤などの強い下剤は、常用すると腸の機能を低下させる可能性があるため、毎日服用することは推奨されません。多くても週1~2回までにするなど、使用回数を制限することや、浸透圧性下剤(酸化マグネシウムなど)、腸への負担が少なく、耐性ができにくい薬剤への切り替えを検討することが重要です。
Q. 下剤ダイエットで、リバウンドは起こりますか?
A. 下剤ダイエットは、一時的に体内の水分や食べたものを排出したことによる見かけ上の体重減少のため、その後の食事などにより簡単にリバウンドが起こります。
また、下剤ダイエットによって腸内環境が悪化すると、代謝が低下し、太りやすい体質になる可能性もあります。
まとめ
この記事では下剤ダイエットのリスクについて解説しました。
下剤ダイエットは、一時的に体重が減少したように見えても、体脂肪が減っているわけではありません。むしろ、下剤の乱用は、脱水症状や電解質異常、腸内環境の悪化など、健康を害するリスクの方がはるかに大きいと言えます。
市販の下剤薬も、安易な使用は避け、必ず医師や薬剤師に相談の上、指示に従って使用することが大切です。
便秘でお悩みの方は、自己判断で下剤に頼るのではなく、まずは生活習慣の改善を心がけましょう。
食生活の見直しや運動習慣の導入、規則正しい排便習慣の確立など、生活習慣を改善することで、便秘の症状が改善されることも少なくありません。
それでも便秘が改善しない場合は、医療機関を受診し、適切な治療を受けるようにしましょう。